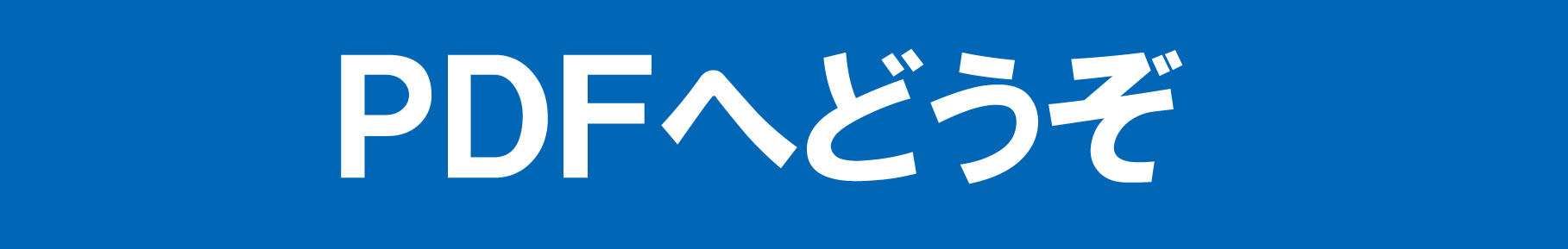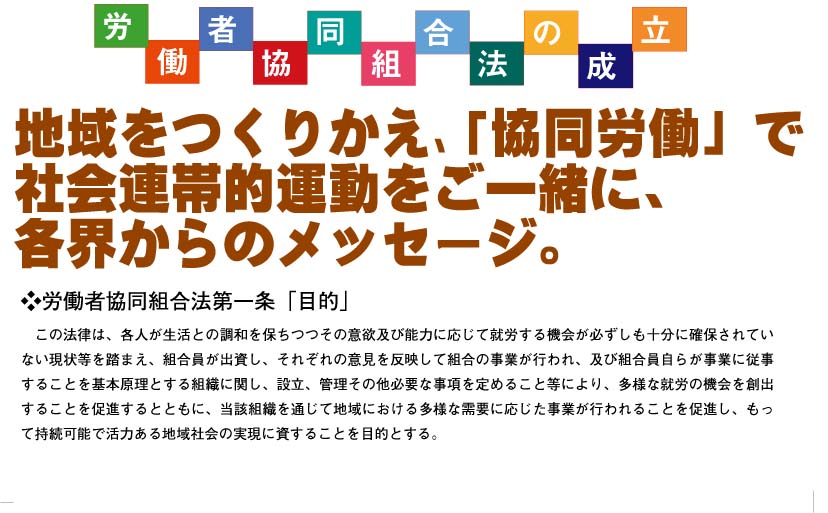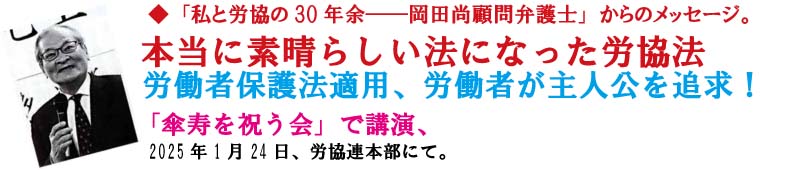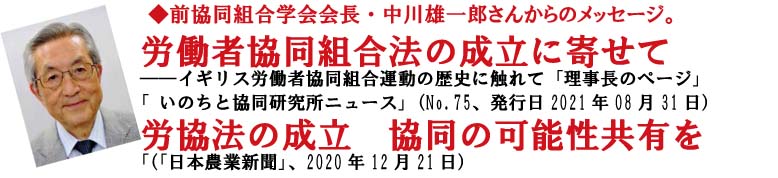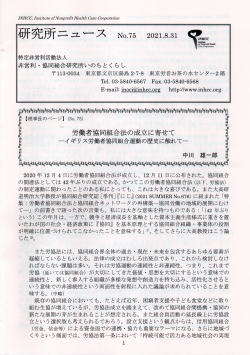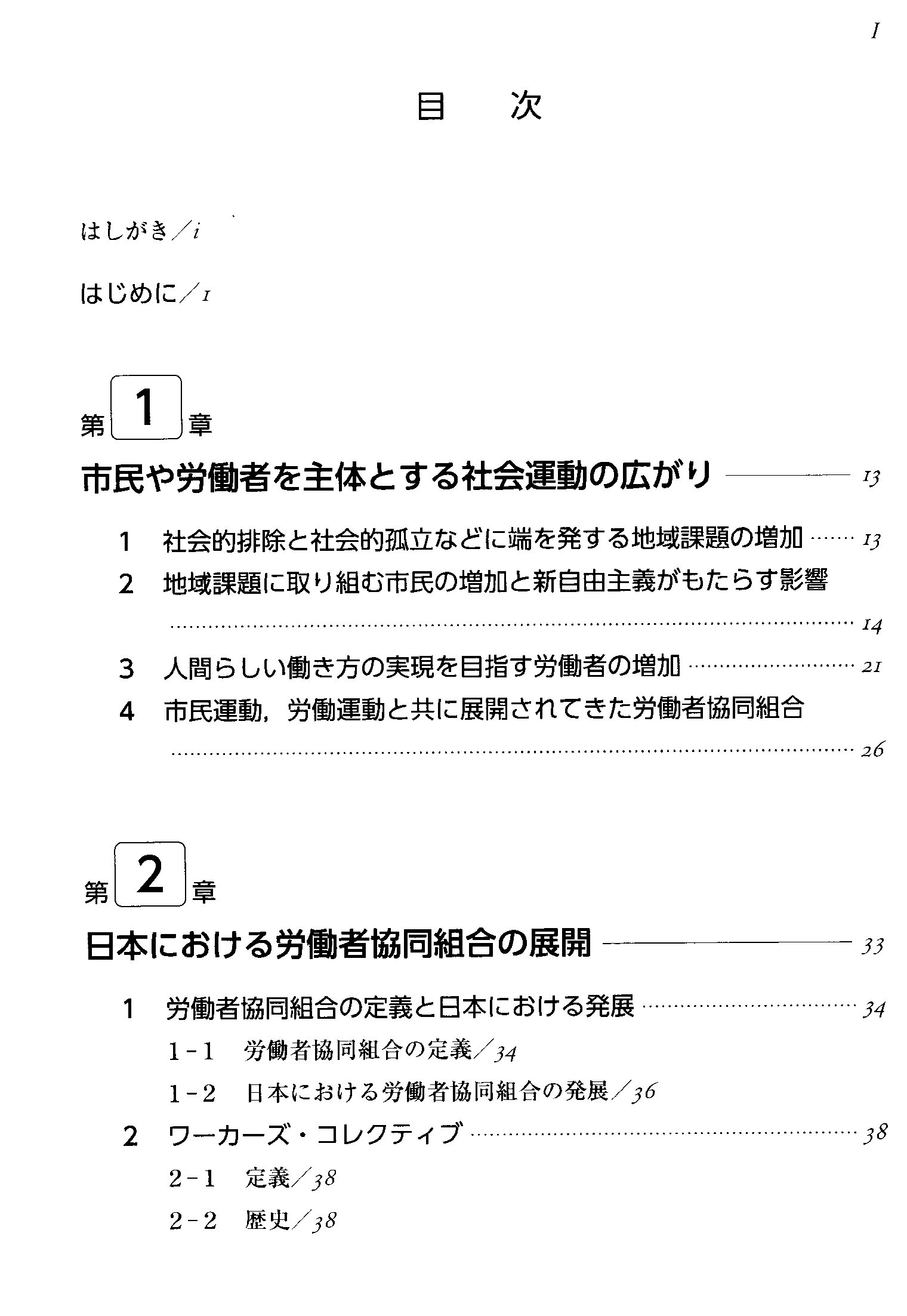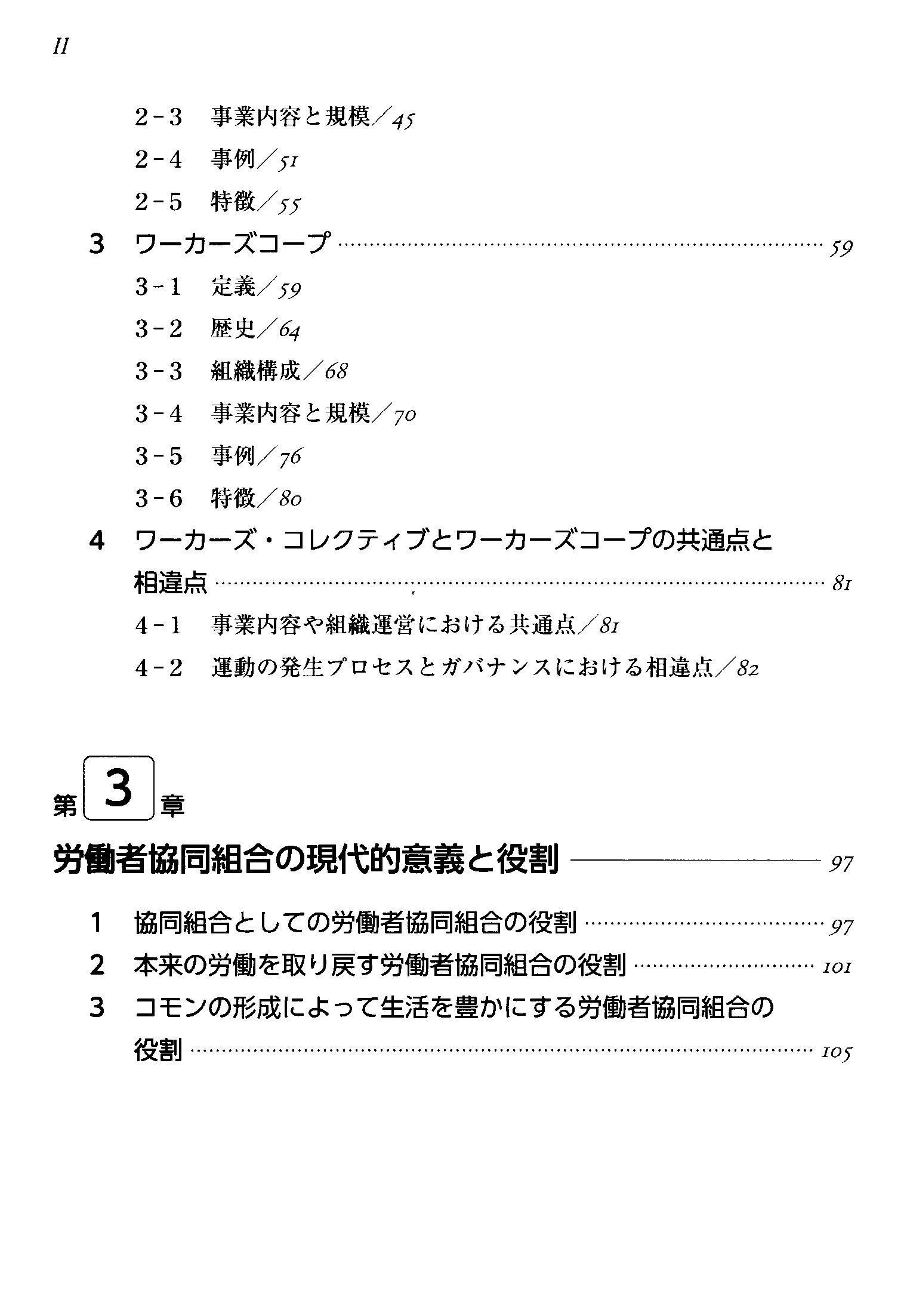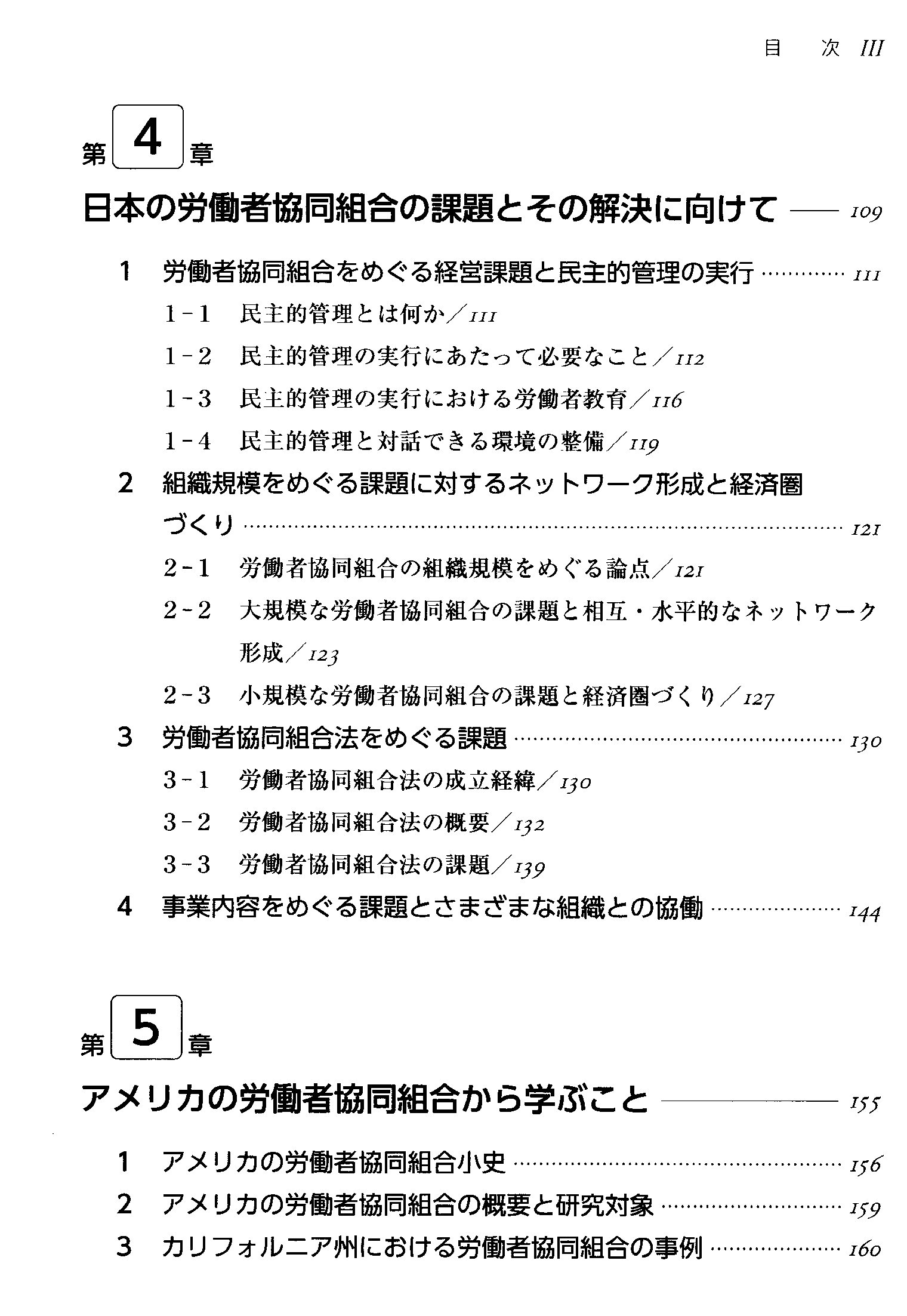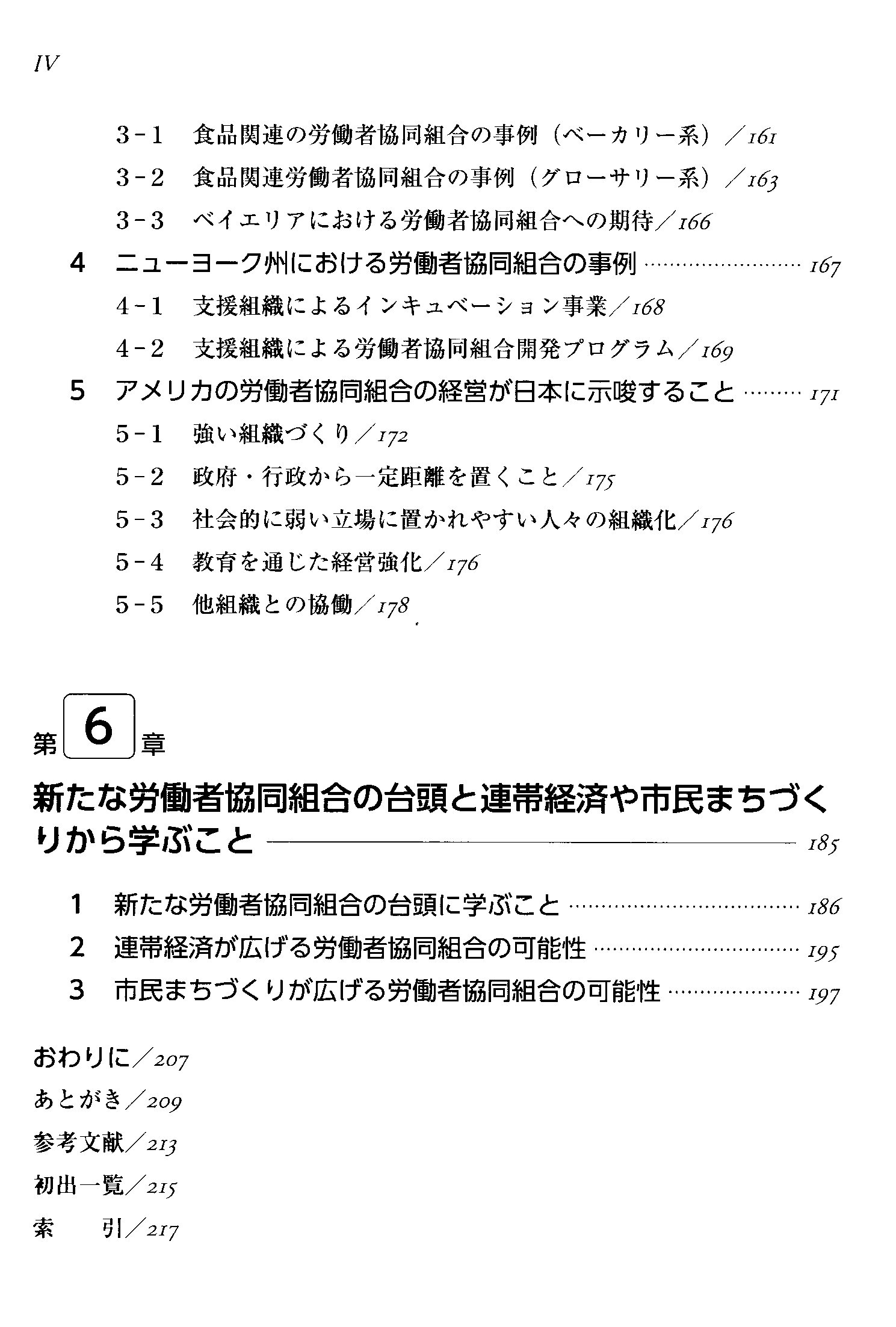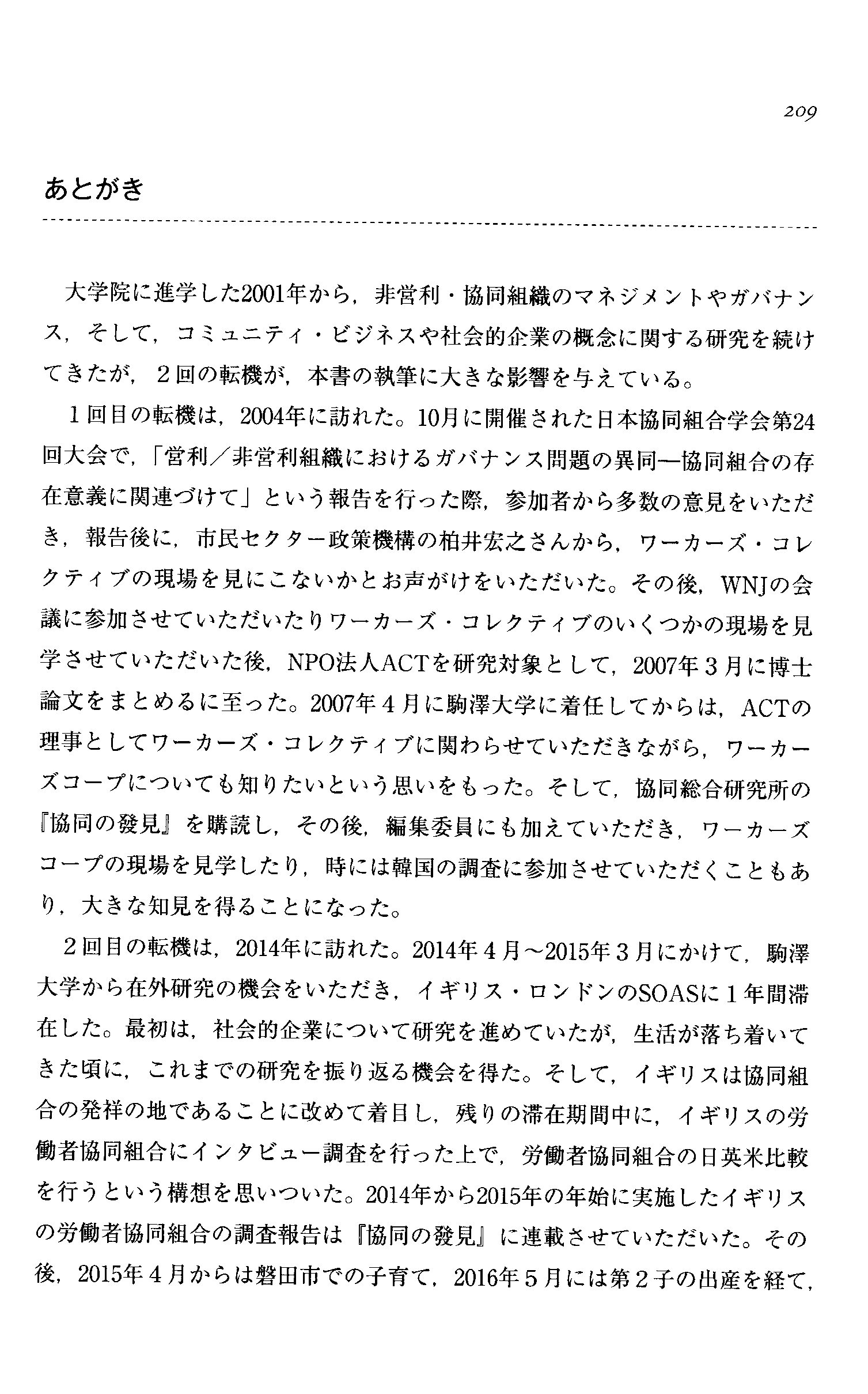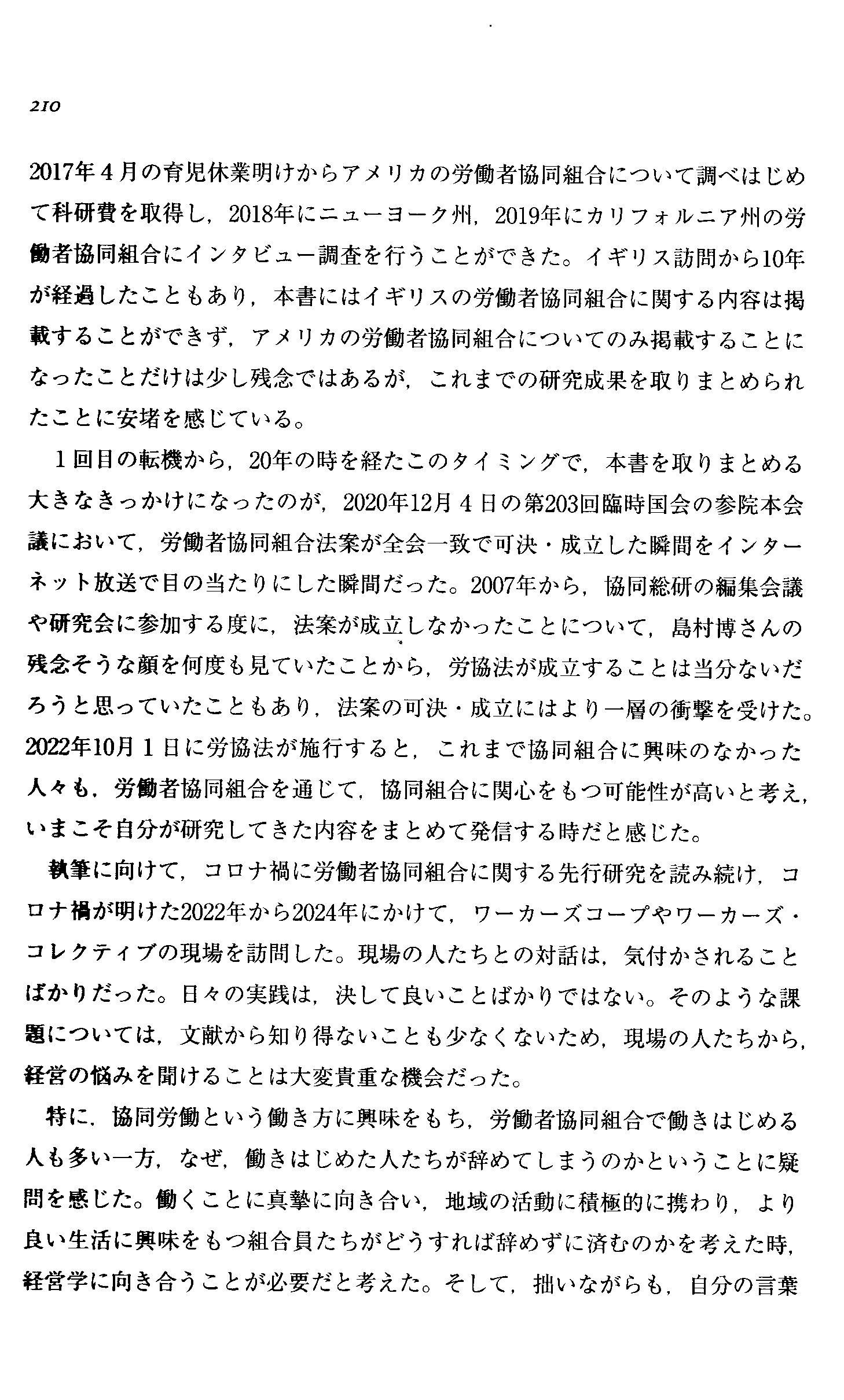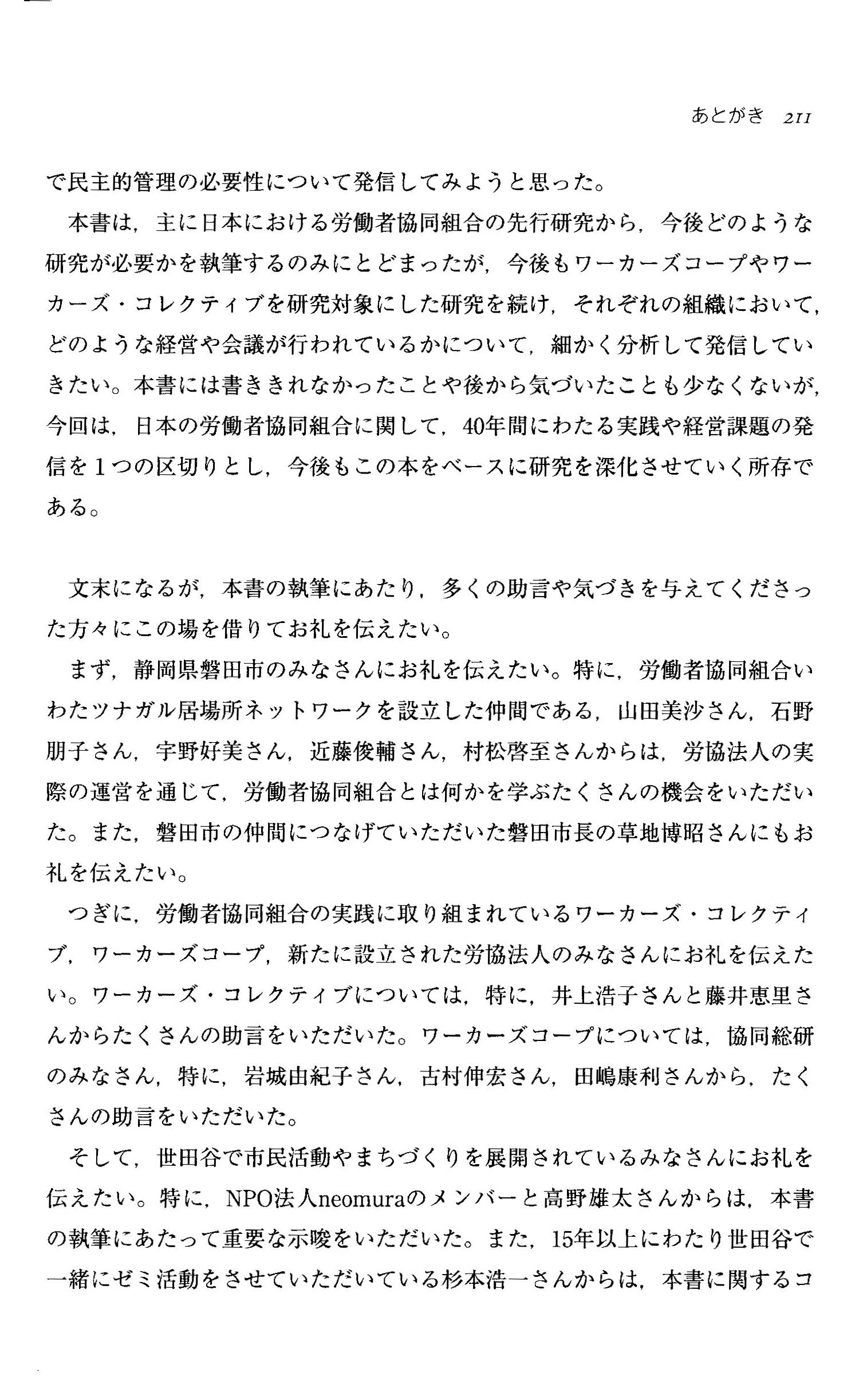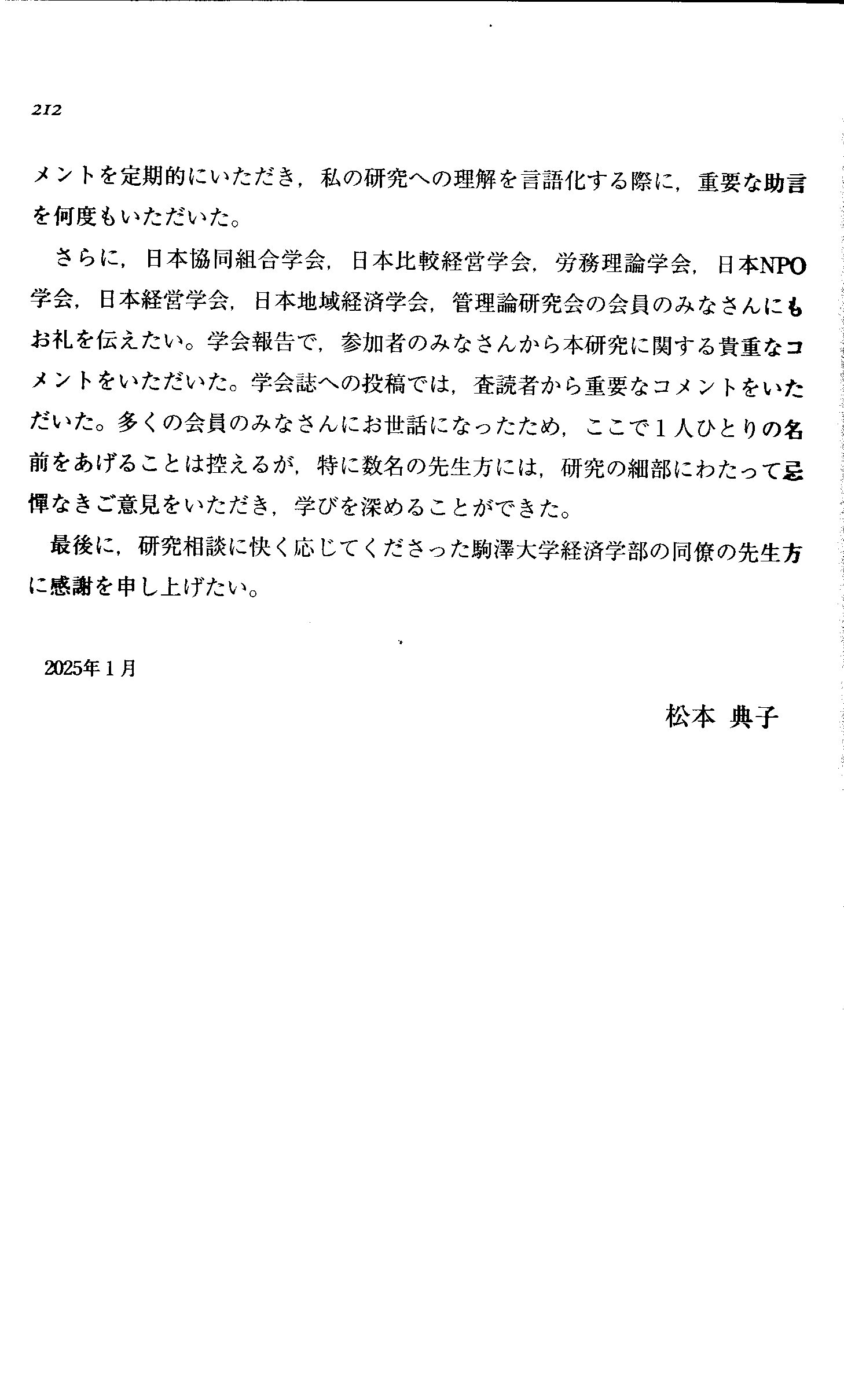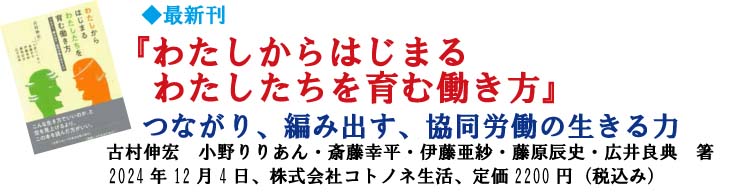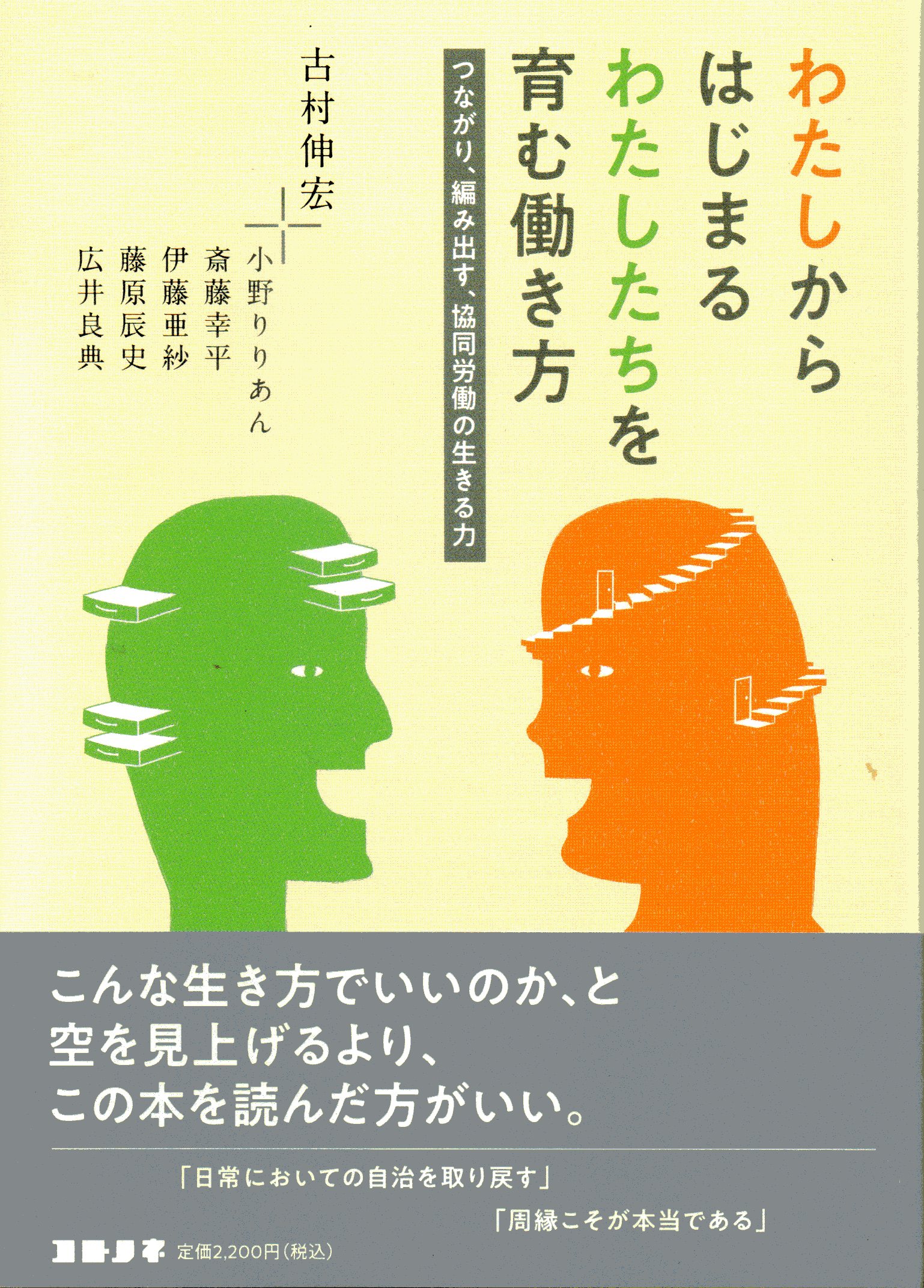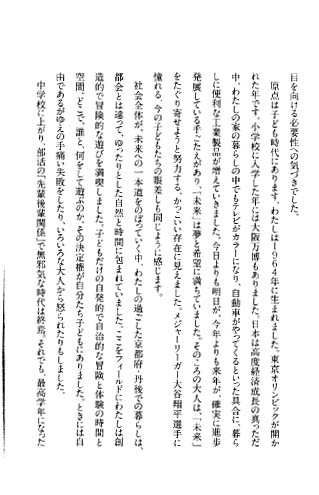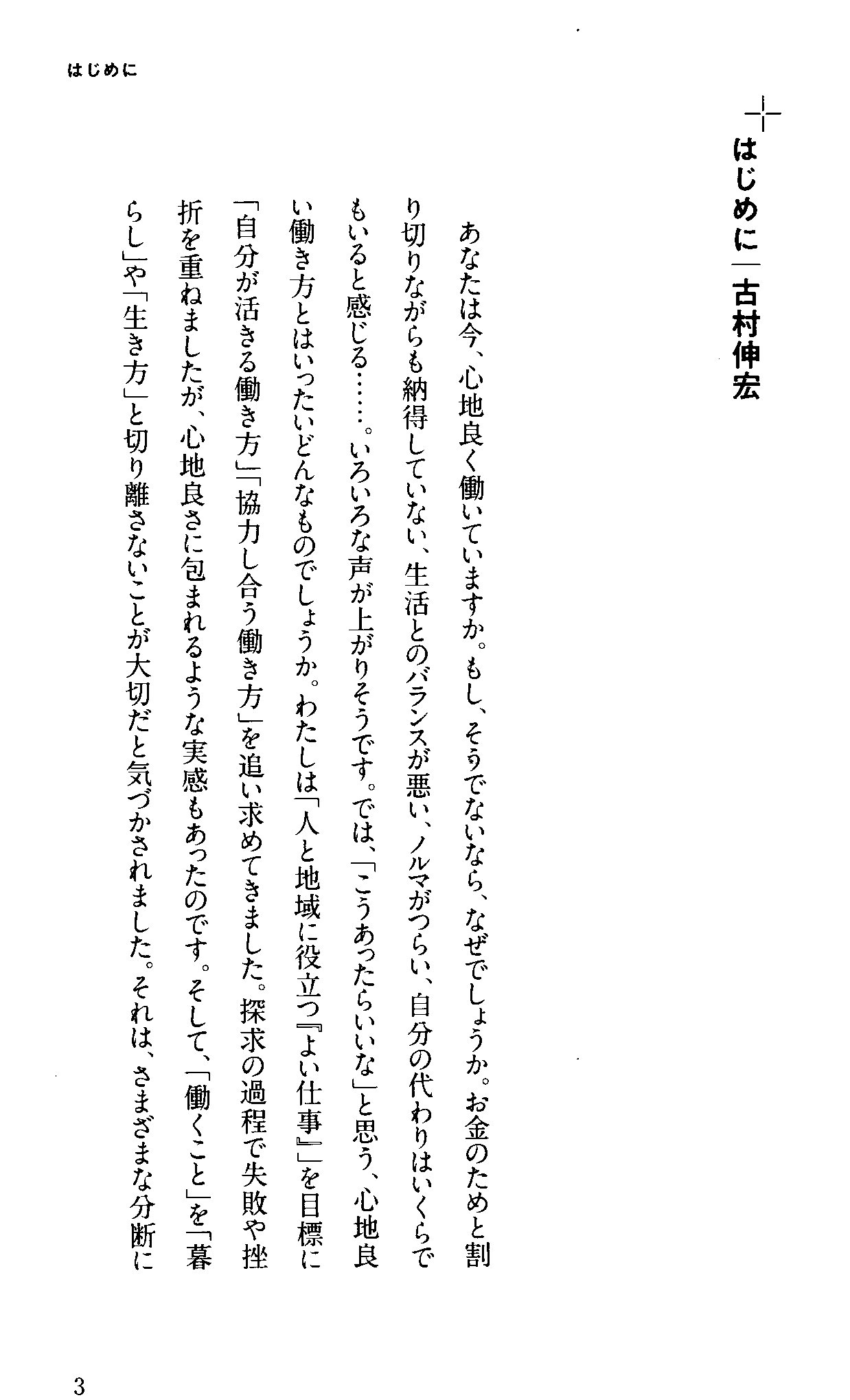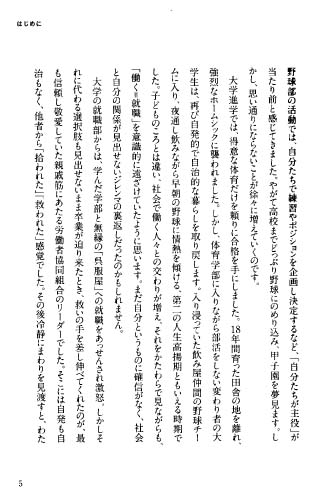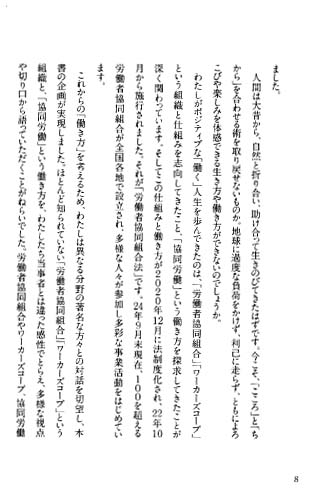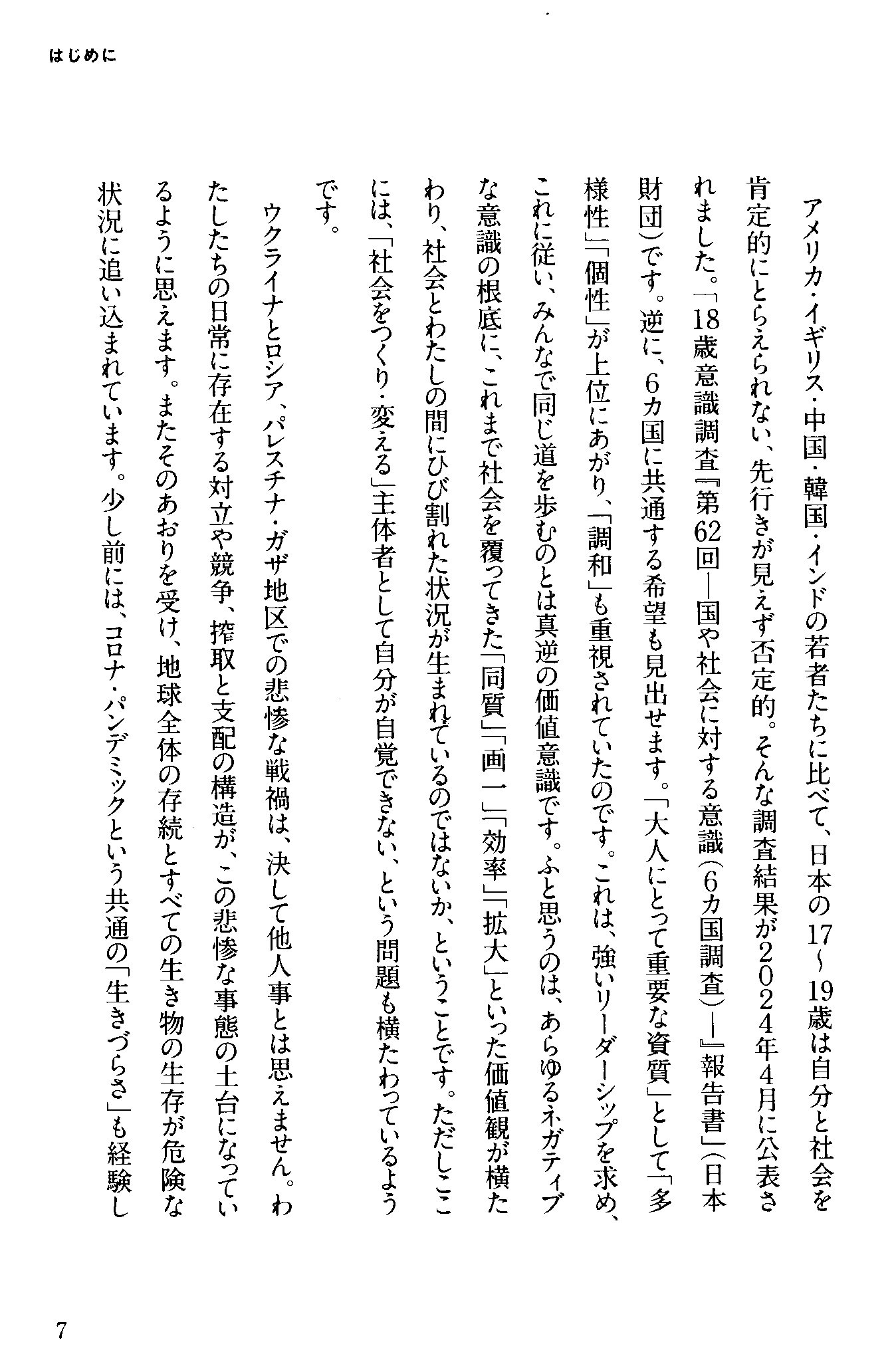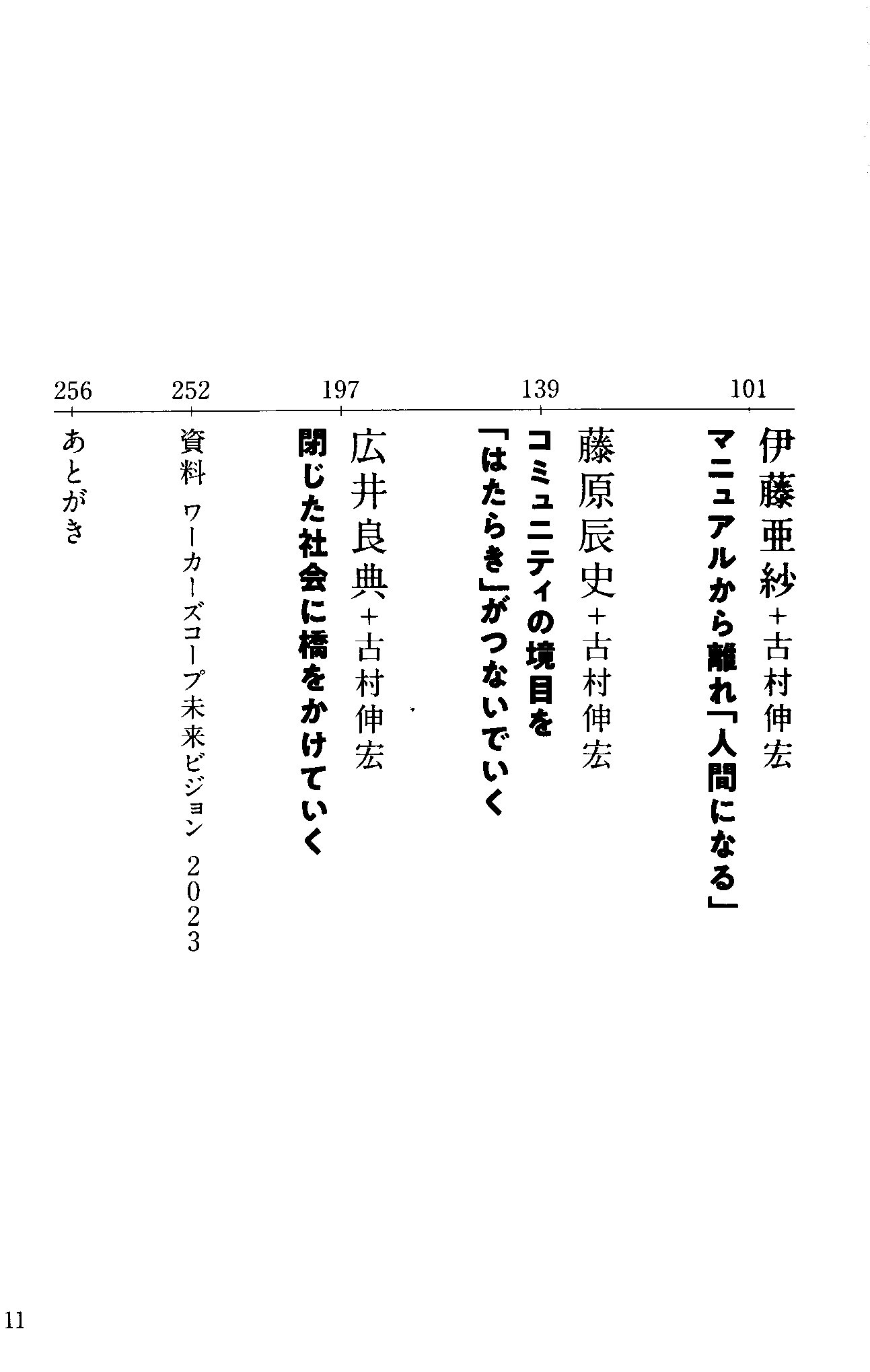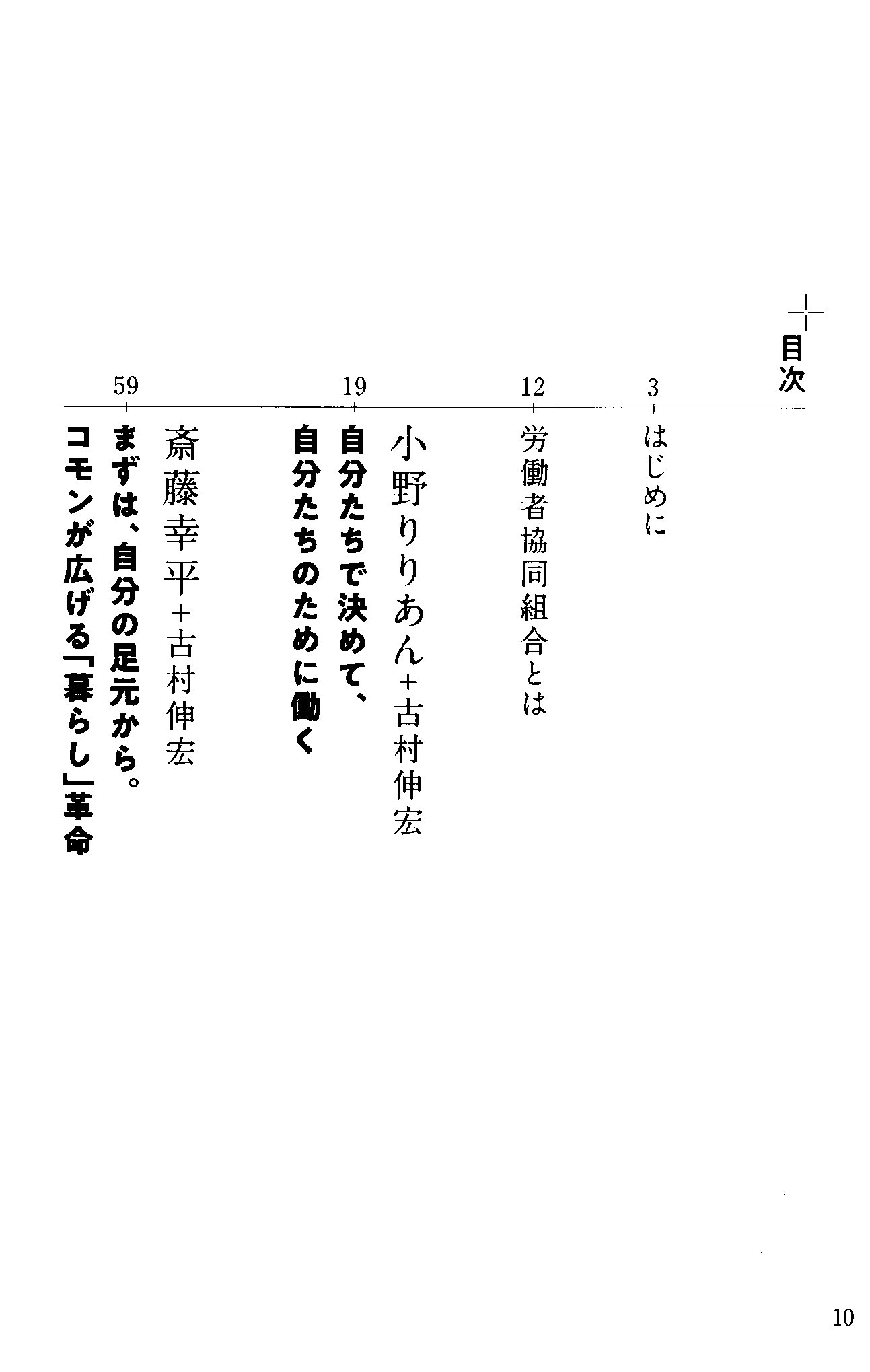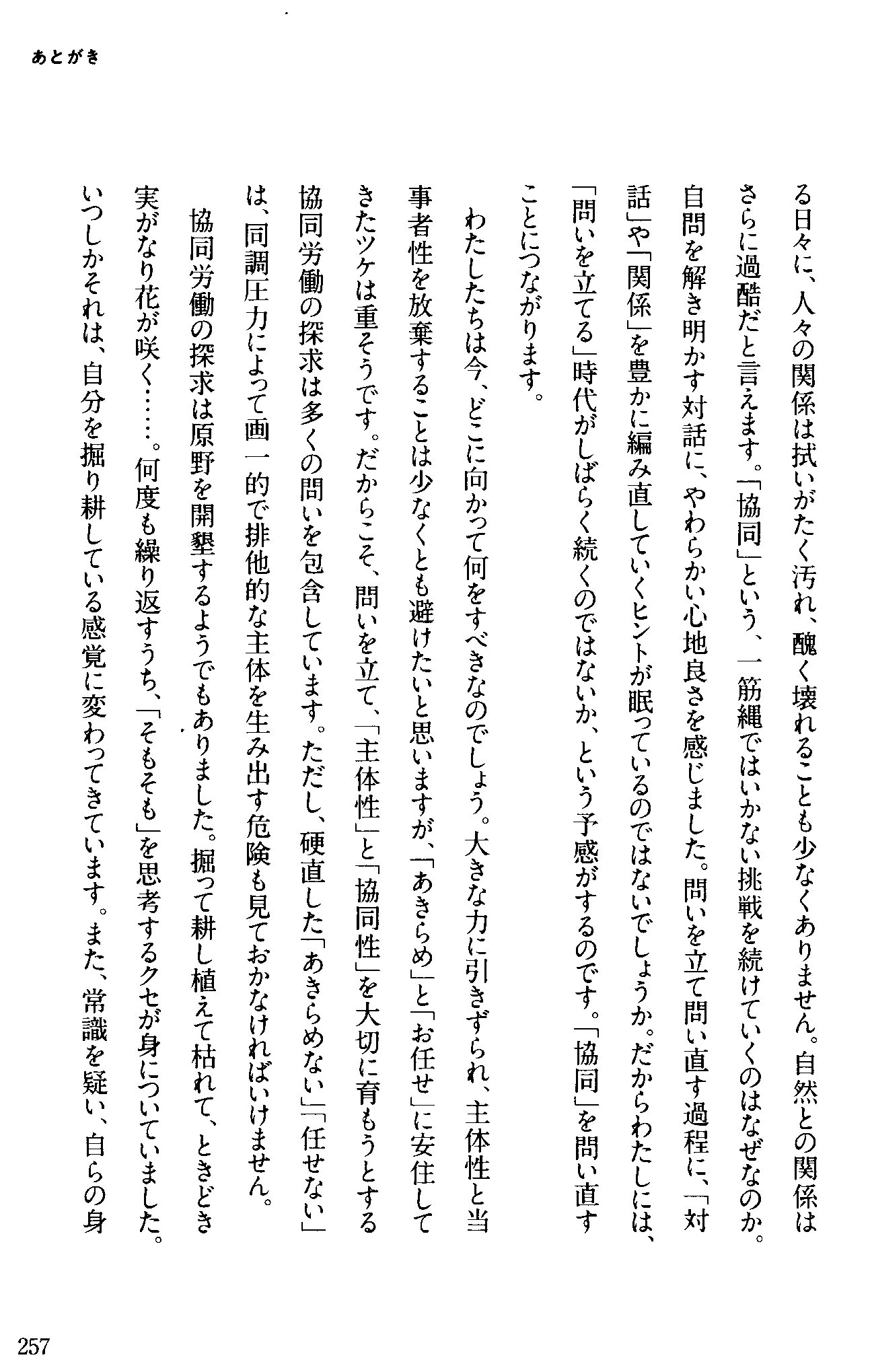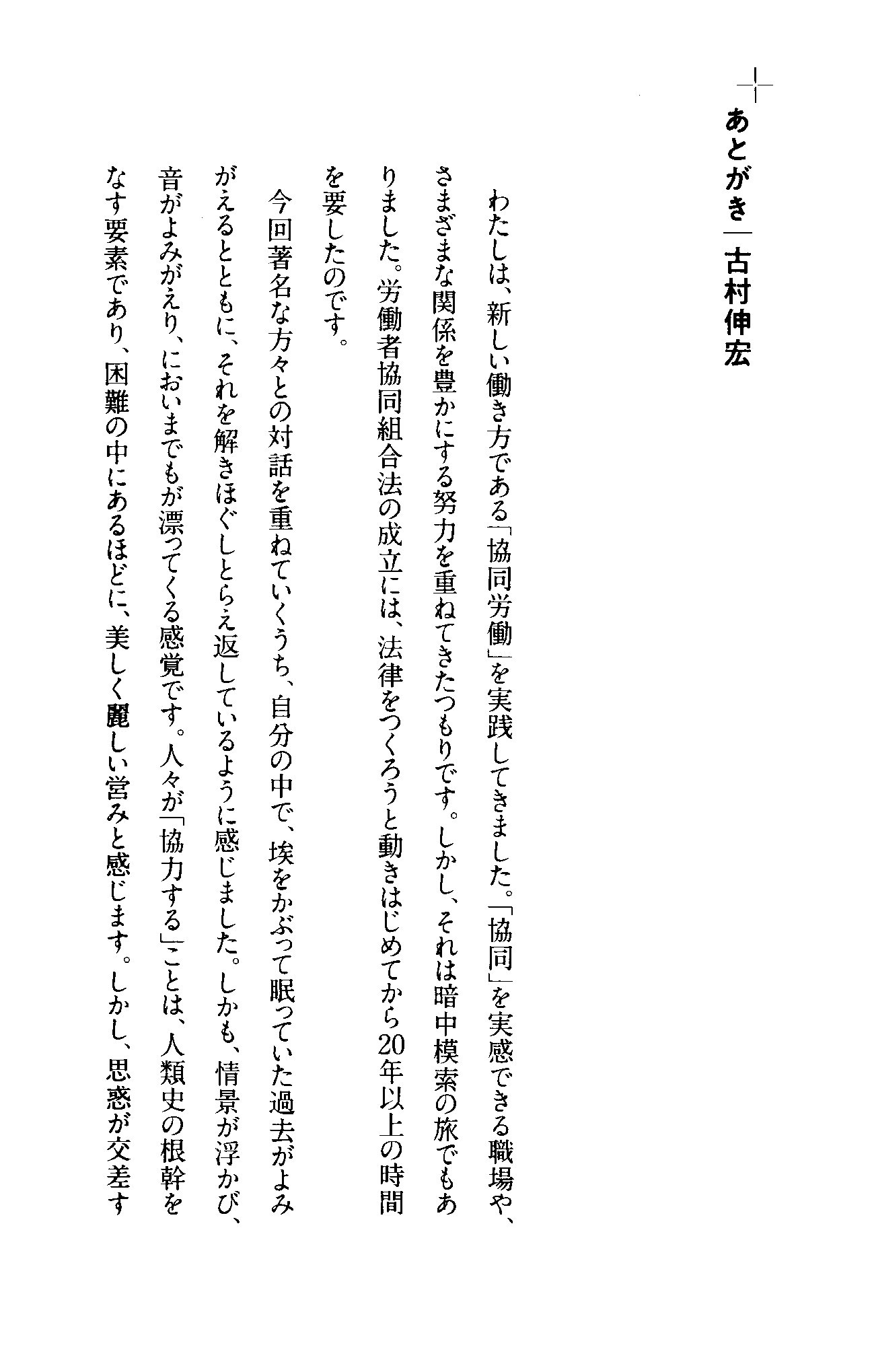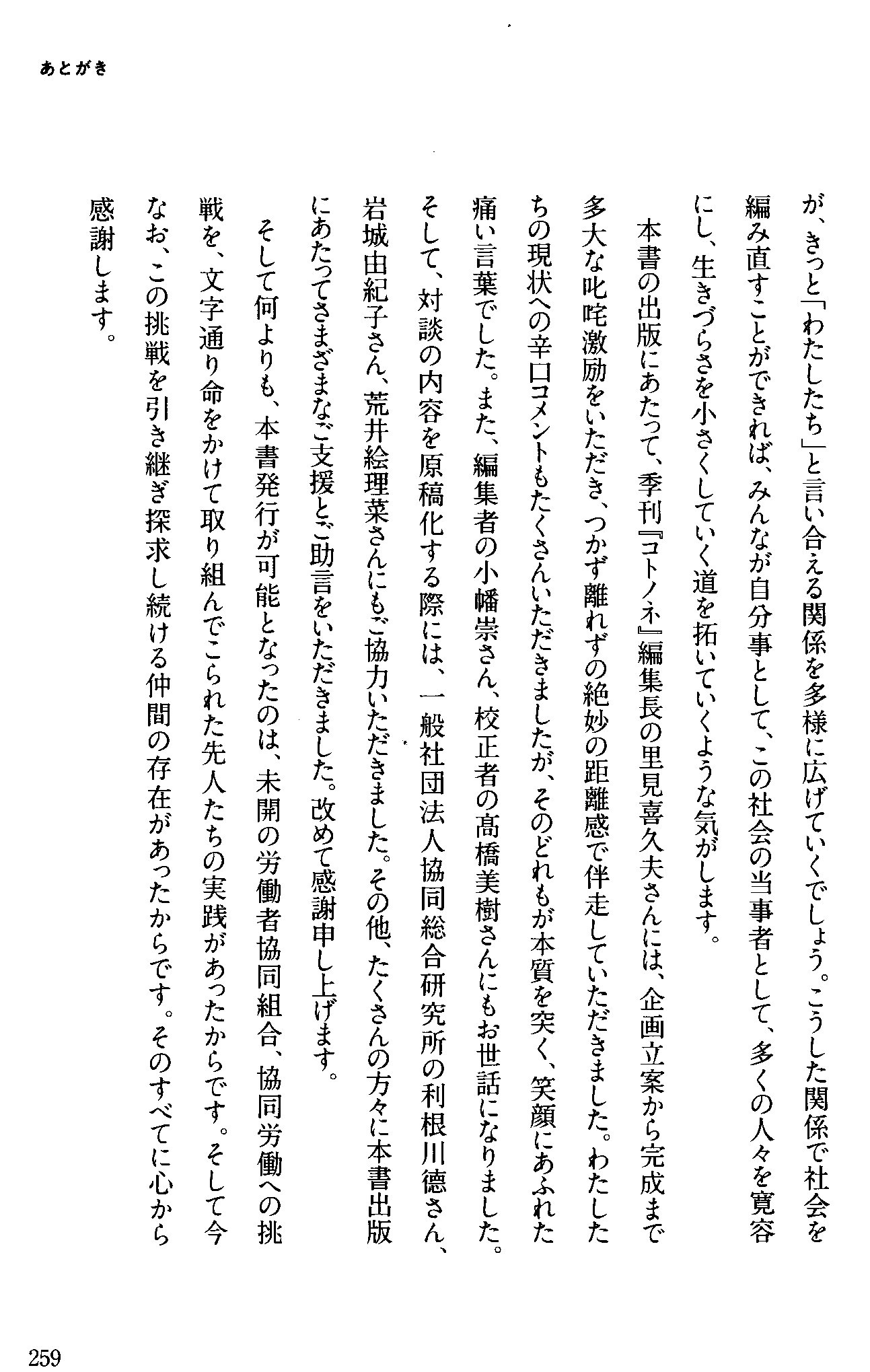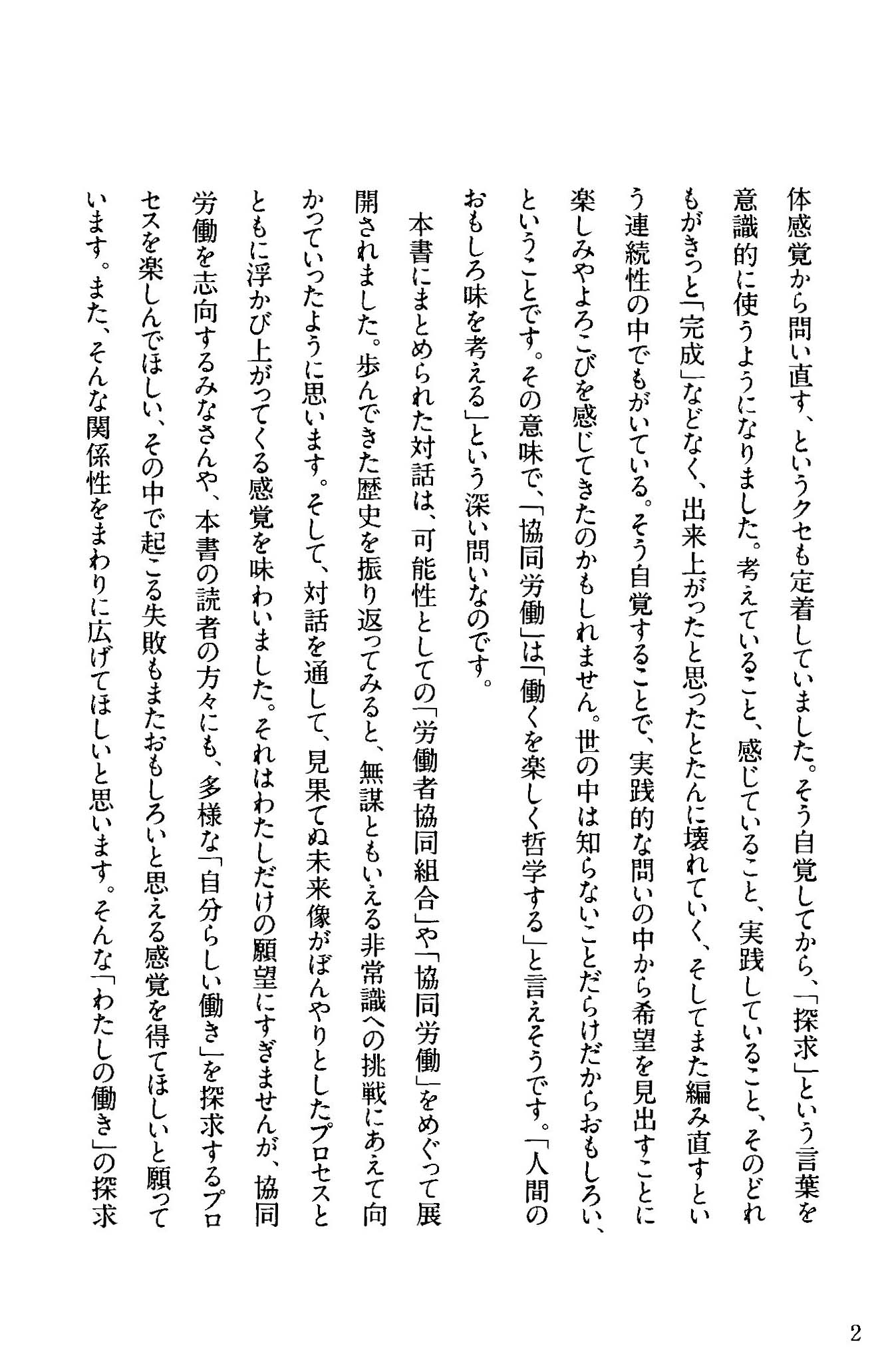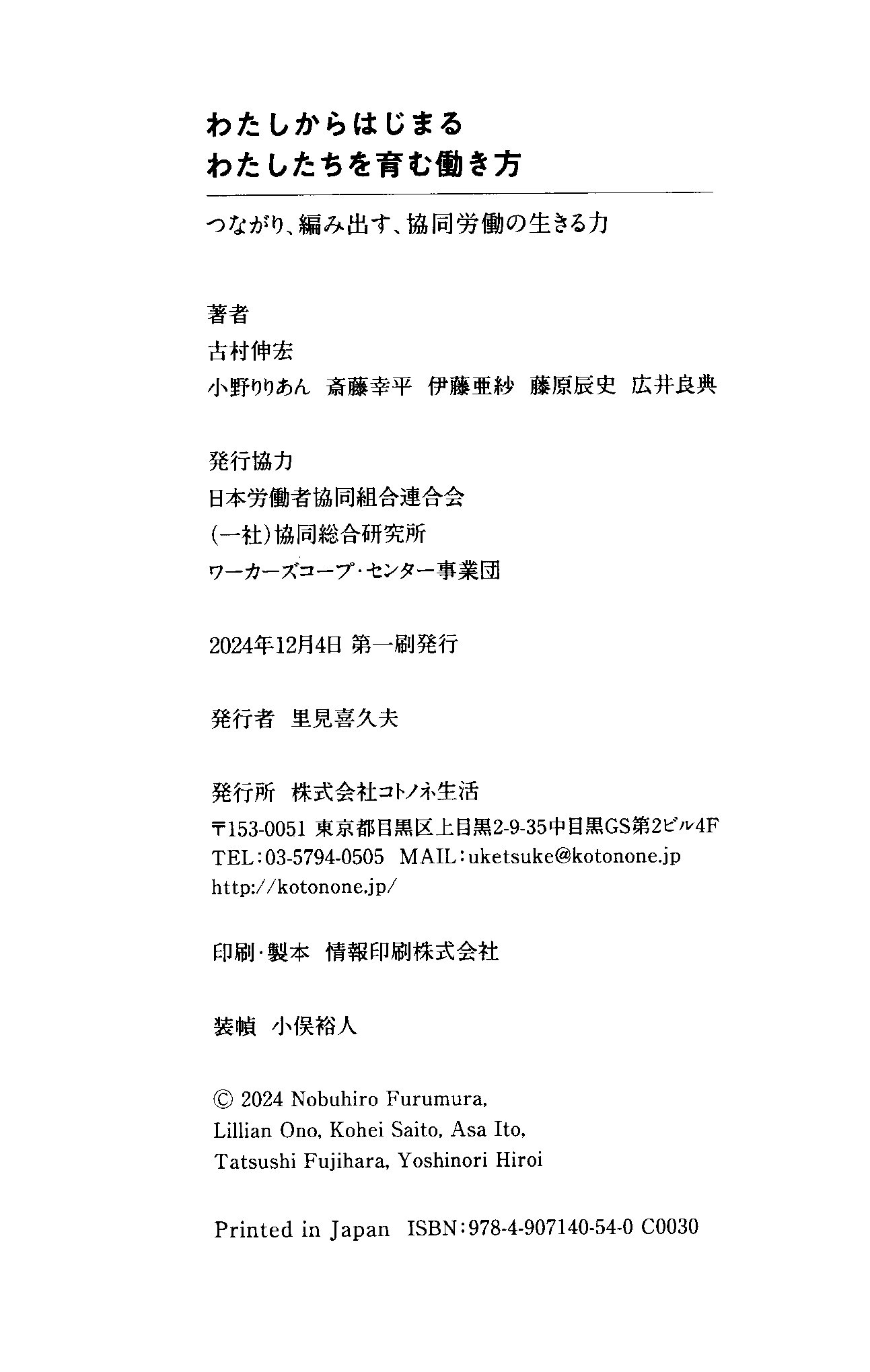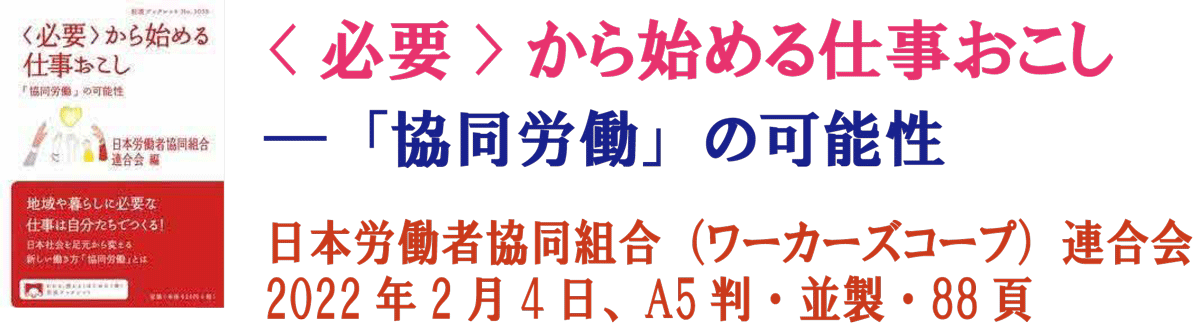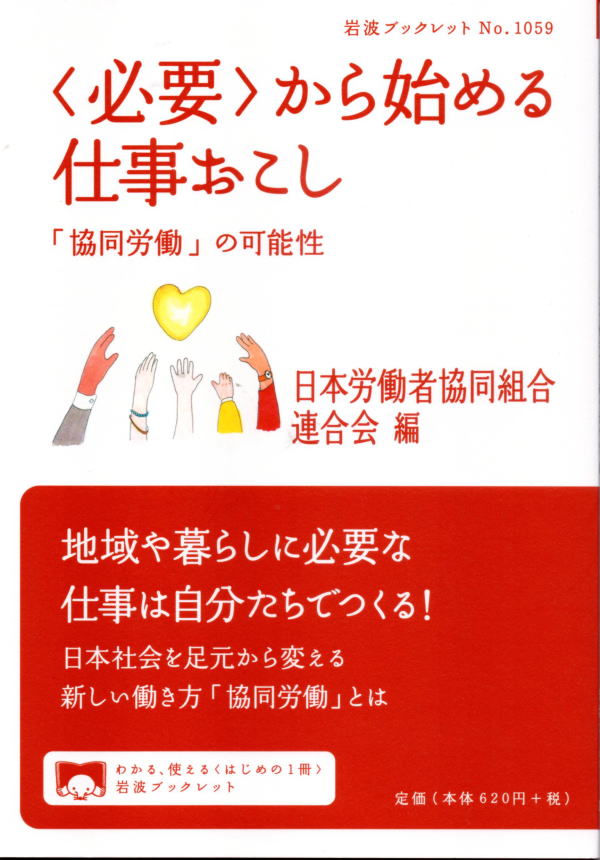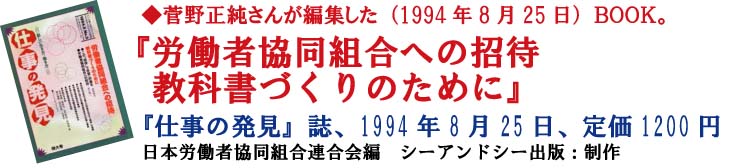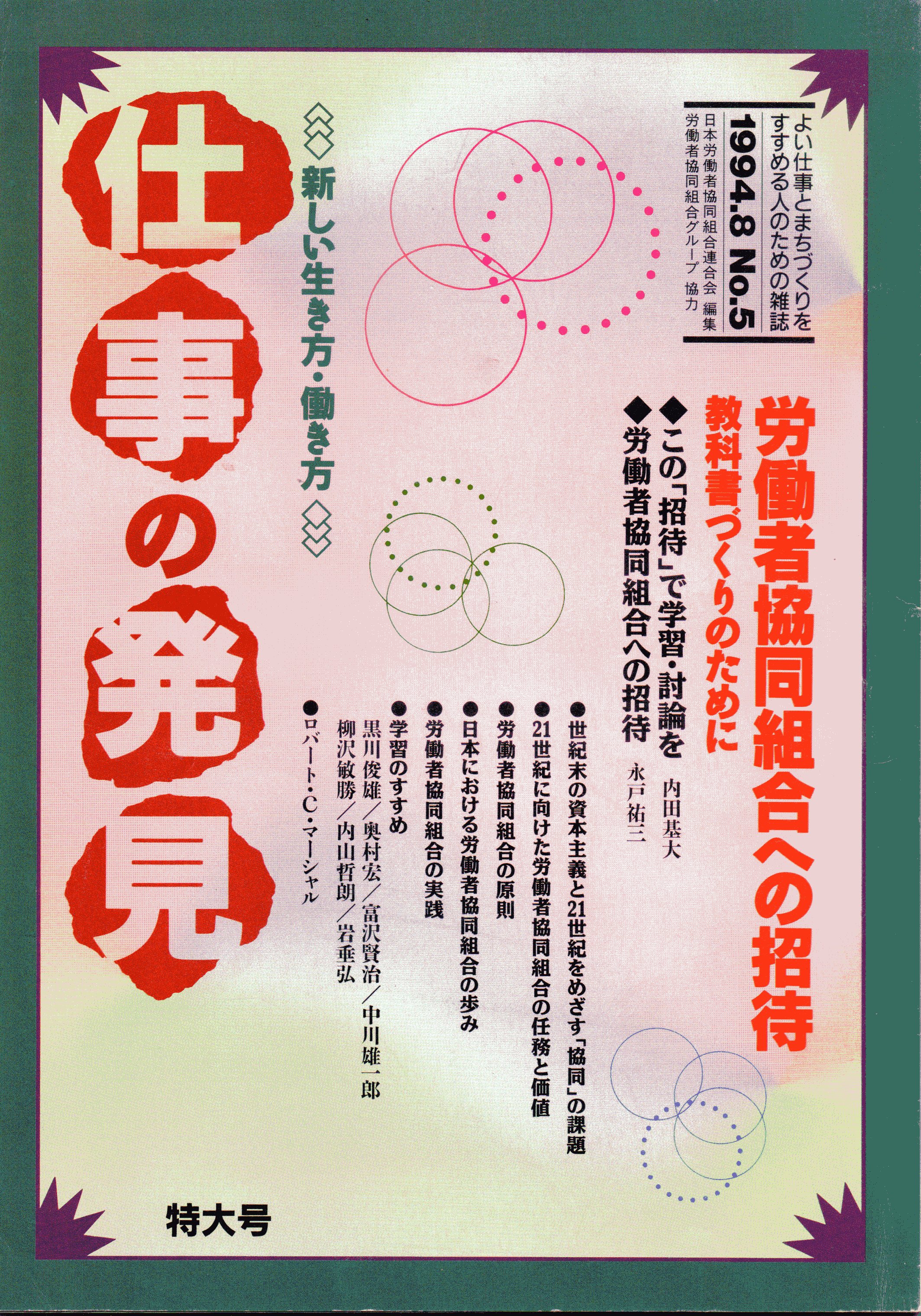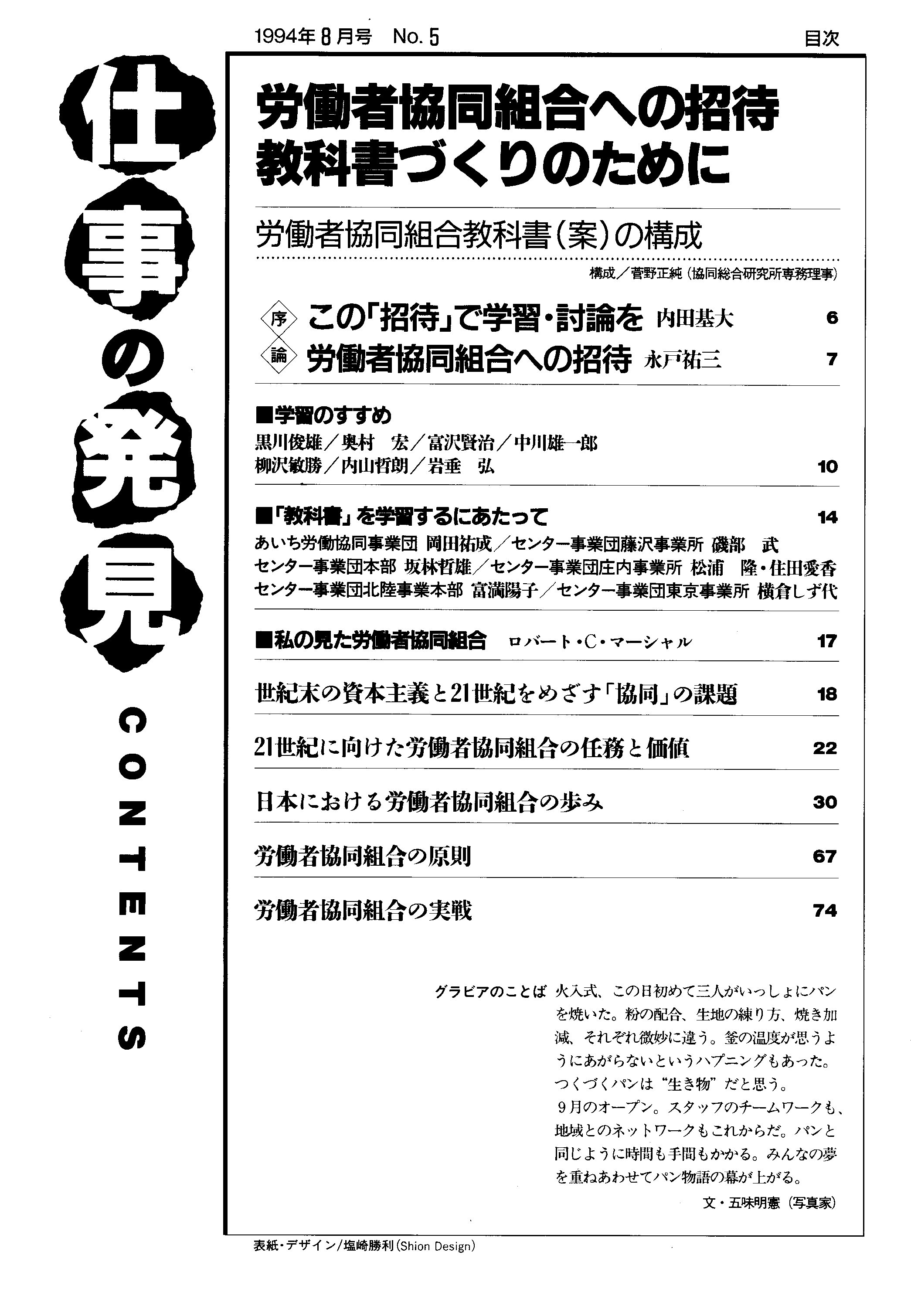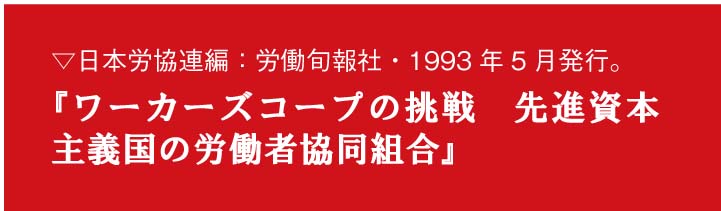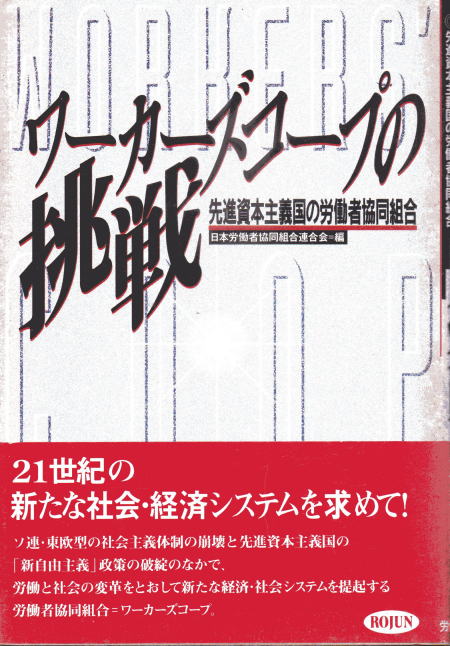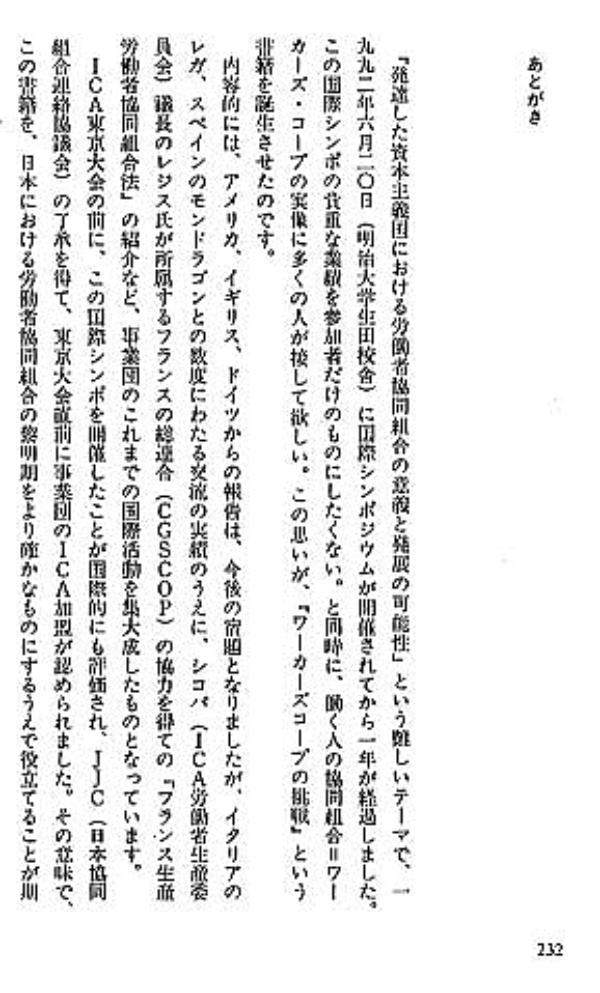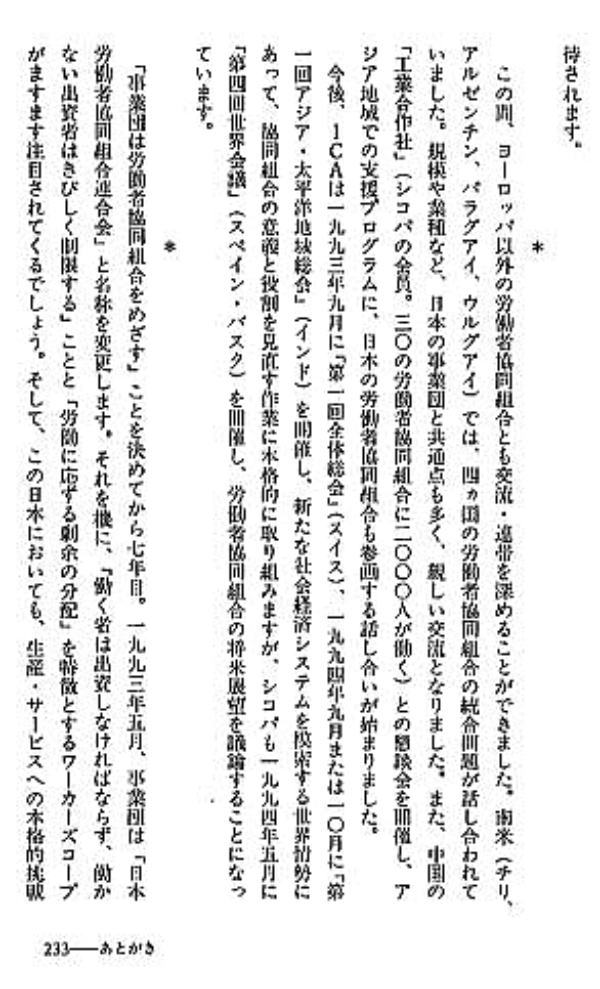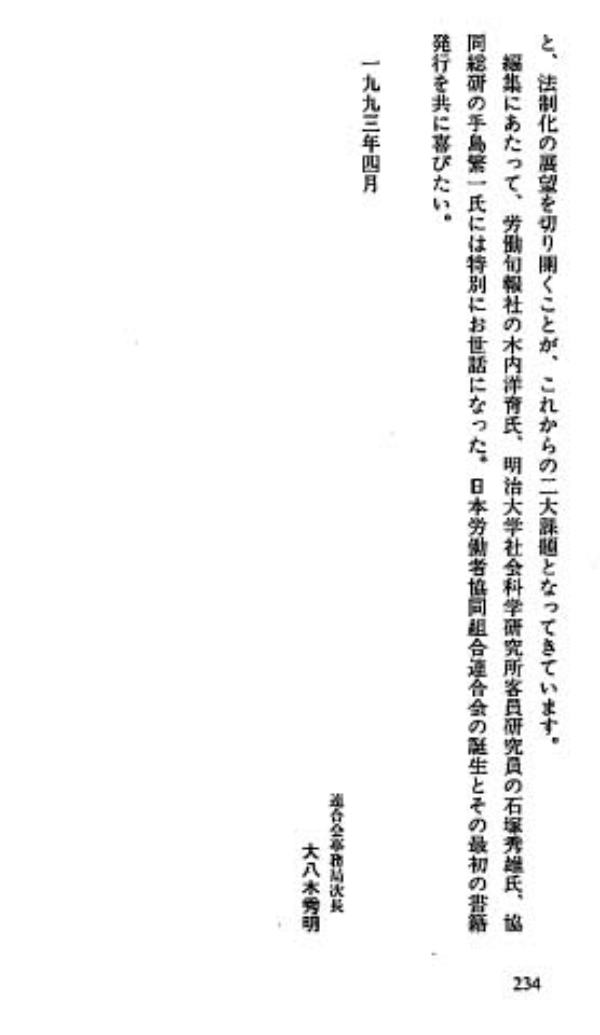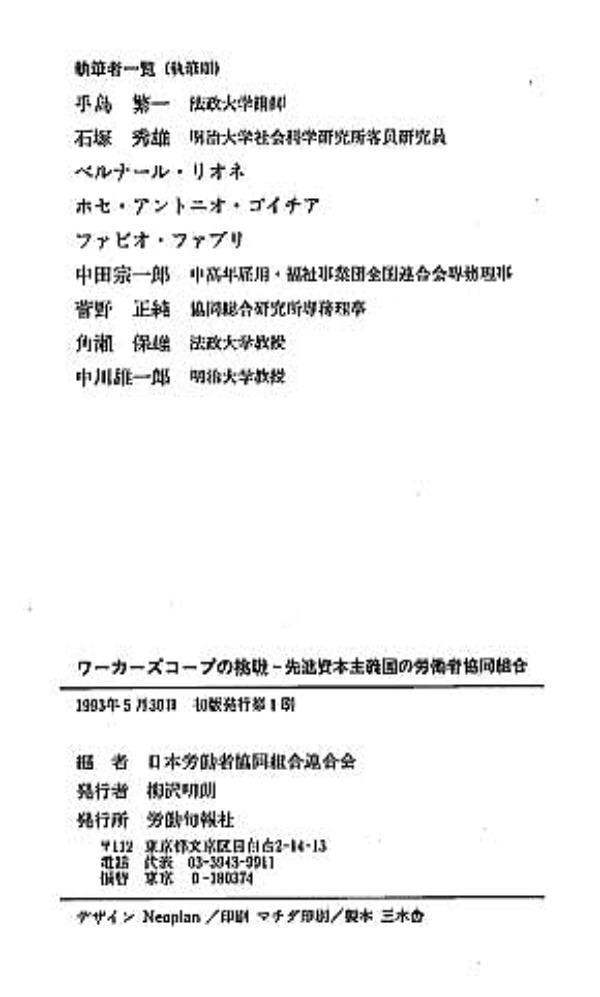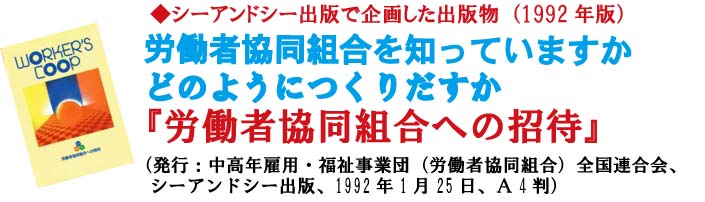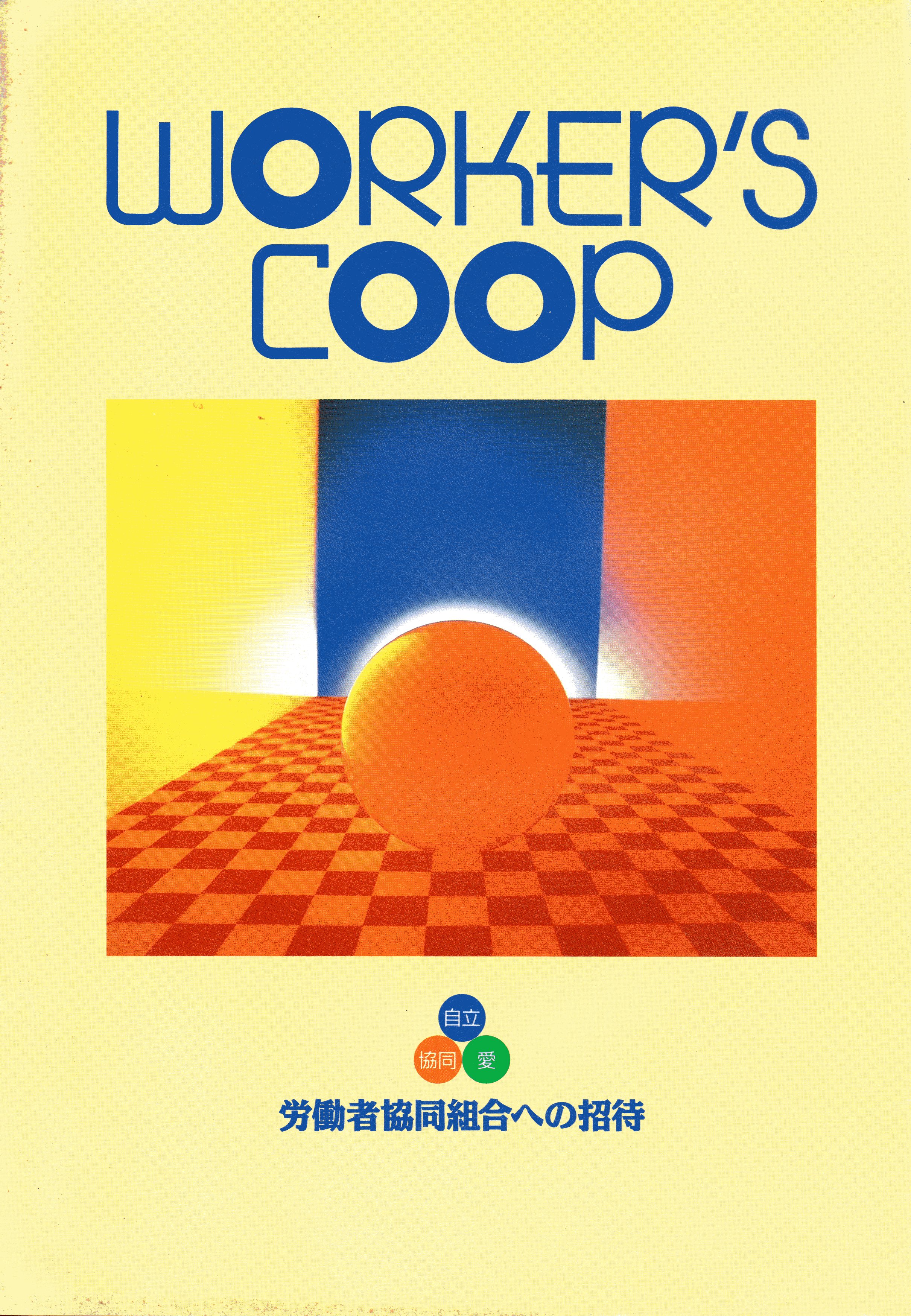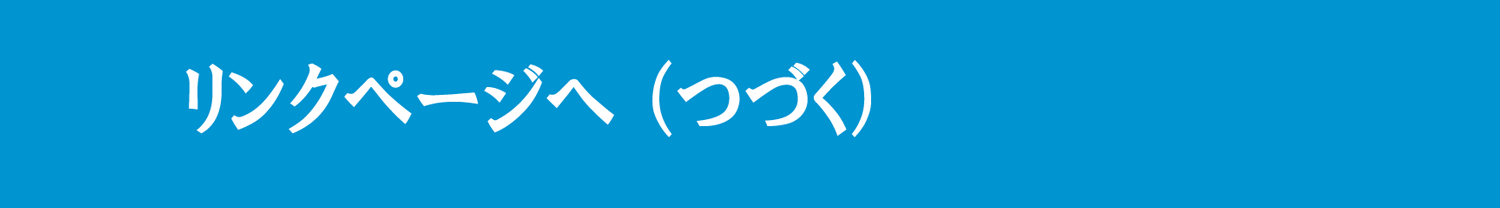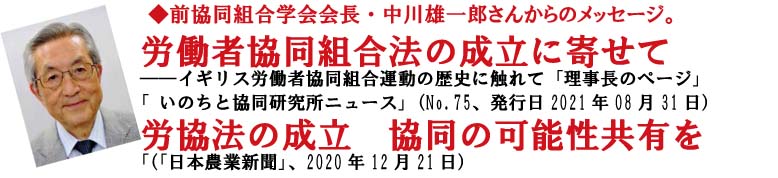
◆「中川雄一郎のページ」(明治大学名誉教授)
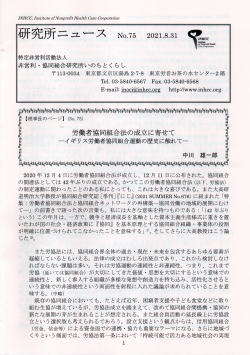
◆更新▽2021年09月12日更新
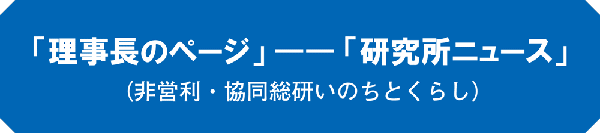
◆2020年12月4日に労働者協同組合法が成立し、12月11日に公布された。協同組合の関連法としては42年ぶりの成立である。かつてこの労働者協同組合法(以下、労協法)の制定運動に関わったことのある私にとっても、これは大きな喜びである。また大高研道明治大学教授が協同組合研究誌[季刊]『にじ』(2021
SUMMER No.676)に組まれた「特集:労働者協同組合法と協同組合ネットワークの再構築―協同労働の地域的展開にむけて―」の前書きで語った次の言葉も、私には大きな意味を持つものである:「(42年ぶりという)この年月は、一方で、競争と経済成長を基軸とした資本主義生産様式に重きを置いたわが国の社会・経済政策に『協同』を基本原理とする協同組合組織・事業体の役割が明確に位置づけられてこなかったことを意味する」(1)。そしてさらに大高教授はこう論じた(2)。
また労協法には、協同組合界全体の過去・現在・未来を包含するあらゆる要素が凝縮しているともいえる。法律の成立はむしろ出発点であり、これから検討しなければならない課題は多い。それは労協運動の連続性と非連続性、つまり、これまで労協(延いては協同組合)が大切にしてきた価値・思想を大切にするという意味での連続性と、新しく参入する組織が多様な発想や創造力を持ち込み、活性化させるという意味での非連続性という両面性を射程に入れた議論が求められていることを意味する。(中略)
既存の協同組合においても、たとえば近年、困窮者支援や子ども食堂などに取り組む生協が増えているが、労協法成立を踏まえて、改めて協同組合間提携・協同の新たな展開の芽が生まれることが想定される。また組合員活動の延長線上に労協設立という選択肢も考えられるであろう。設立支援という観点からは、信用協同組合(労金、信金等)による資金面での連携・協力も重要なテーマになる。さらに地域づくりという側面では、労協法第一条において「持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする」と記されているように、地域の現実とニーズに即した多様で主体的な住民の仕事づくりが目指されることになるが、特に第一次産業にかかわる協同組合(農協・漁協・森林組合等)との連携も重要な課題となってくるであろう。(後略)
私は、このような特性と可能性を内包している労協が労協法に基づいて実際にその事業と運動をどう展開し、それらの成果と能力をどう発展させ、蓄積していくのだろうか、しばし考えてみた。そしてその時に私が参考にした資料が、1999年11月に東京において開催された「労働者協同組合研究
国際フォーラム」で報告された、今は亡き(労働者協同組合連合会元会長)菅野(かんの)正純(まさずみ)氏の「協同の新しい可能性に向かって」であった。
私は、あの国際フォーラムでの菅野氏の報告からおよそ21年後の2020年12月21日付け日本農業新聞の『論点』欄に「労協法の成立:協同の可能性共有を」と題した一文を草し、そのなかで「菅野氏の報告」の一部を書き記しておいた(3)。「協同の新しい可能性に向かって」と題する菅野氏の報告は、今読み直しても近未来的な「労協の理念」とでもいうべき適正さを強く示唆するものである。すなわち、
① 協同労働は雇用労働に代わる選択肢である。② この選択肢を保障する社会制度を創り出すことの必要性。③ 21世紀を目前にして、労協は組合員の利益のみならず、地域コミュニティと社会全体の利益を追求する「21世紀型協同組合」としての「新しいワーカーズコープの法制度」を提案し、ボランティアや利用者と共に組合員が協同する協同組合を、またハンディキャップを持つ人も組合員となり、かつ労働する主人公になっていく協同組合を目指す。④ これからの時代は、若者たちが人びとの共感のなかで自分らしい仕事を見出し、自分らしい人生を切り開いていくための「援助のための基金」が重要な課題として労協に求められるであろう。
さらに菅野氏は、④の「援助のための基金」についてこう言及した:労協はその「公共的使命」のための「新しい労協財政のあり方」を追求していく。それは、「組合員の営々たる労働のなかで作り出された剰余金、就労創出の積立金、福祉基金、それに教育基金」を組合員だけでなく地域コミュニティの他の人たちも利用できる「新たな仕事起こしを実践する連帯支援資金」となるだろう。
菅野氏のこの労協アイデンティティについて、すなわち、労協が労協である所以(ゆえん)について、「自立した個人は社会で生きる自覚を意識する」とのヘーゲルの「承認の必要性」を援用して言い換えるならば、次のように表現できるかもしれない:市民の「労協に対する期待」、市民のために「労協の果たすべき役割」、そして市民と共に「労協のなし得ること」の実体を明らかにすることである。要するに、「協同労働」が「生活と人間性に不可分な労働である」と人びとによって認識されるのであれば、労協こそ「労働者の裁量と自律性を発揮するのに相応しい『場』である」と、言うことになるだろう。
1980年10月に開催された第27回ICA(国際協同組合同盟)モスクワ大会で採択された『レイドロー報告』(『西暦2000年における協同組合』Co-operatives in the Year 2000)第V章「将来の選択・第2優先分野:生産的労働のための協同組合」(Co-operatives for Productive Labour)は大きな関心を呼んだ。それはレイドロー自身が述べた次の主張に見て取れる(4)。
労働者協同組合は、雇用や所有者感覚よりももっと深い内面的なニーズ、すなわち、人間に特有な個性と労働との関係に触れることになる。 1978年に開催された「西暦2000年への挑戦」と題するユネスコの会議で、ブカレスト大学教授は、肉体労働と知的労働の適正な調和を図ることの必要性と、あらゆる最高の価値基準のなかに労働の観念を生活や人格形成に不可欠なものとして取り上げる必要性について述べている。労働者協同組合に関わるこの思考は、従来の伝統的な被雇用者と作業場の関係とを比べてみれば、教授の発言の趣旨にはるかに近いものである。
ところで私は、上記「菅野氏の①~④の報告」を書きながら、イギリス産業革命後期における生産者協同組合をめぐる労働制度について――1891年に『イギリスにおける協同組合運動』を著わした――ベアトリス・ウェッブと対立し論争したキリスト教社会主義者J.M.ラドローの主張を思い出していた。彼はTracts on Christian Socialismでこう強調した(5)。
今やわれわれの任務は、キリスト教社会主義者の目的がいかなる機構によって成し遂げられるのかを明らかにすることである。すなわち、労働者はどのようにして競争制度の下での個人的労働の束縛から自らを解放することができるのか、また自らを解放するために他の人たちの援助を得ることができるのか、あるいは少なくとも現在どの程度まで労働者は誠実な同胞関係(fellowship)によってその弊害を軽減できるのか、ということなのである。この機構を他の人たちに提示する際にわれわれは、社会を車輪やスプリングの単なる集合と見なし、生きた人間の協力関係(partnership)と見なさず、また社会に活気を与える形式のみを考慮して、その精神を考慮しない社会機構の盲目的崇拝に異議を唱えなければならない。
ラドローがここで主張していたことは、“競争制度の下に置かれている個々の労働者は、いかにして労働の束縛から解放されるのか”、“労働者は、労働の束縛から自らを解放するために、いかにして他の人たちの援助を得ることができるのか”、そして“労働者は誠実な同胞関係、すなわち、連帯意識を以てすれば、競争制度の弊害を軽減することができるのか”、ということであった。簡潔に言えば、“資本主義的競争下において労働者はどうすれば「協同労働」を実現することができるのか”、である。ラドローは、1848年から1850年初期にかけて、キリスト教社会主義思想に基づいた「協同労働の実現」のための社会改革を唱え、「労働を基礎とする社会的な人間関係のあり様はいかにあるべきか」を人びとに問いかけた。こうしてラドローは、同じキリスト教社会主義者のE.V.ニールやトマス・ヒューズなどと共に労働者生産協同組合運動を支援したのである。
他方、あのロッチデール公正先駆者組合は1854年までに生産事業の「小麦製粉」から手を引き、購買協同組合としてその精力を費やしていった。すなわち、先駆者組合は一時、その発展・成長を背景に、設立10年後の1854年10月の総会において新規約である「1854年規約第2条」に「先駆者組合の目的」として次のような文言を付したのである(6):「本協同組合の目的は、一般の商人(dealers)の取り引きと同じように経営することにより、組合員が食料品、燃料品、衣料品、あるいはその他の生活必需品をより有利に購入できるようにする基金を組合員の自発的出資により調達することである」、と。
これに対して、ラドロー、ニール、そしてヒューズなどを中心とするキリスト教社会主義者たちは、彼らの努力を「協同組合法」の成立に注いだ。こうして彼らの努力により1852年に世界最初の近代協同組合法「産業および節約組合法」(〈The Industrial and Provident Societies Act〉―正確に訳すと「産業労働および共済組合法」であるかも知れない)が成立する。日本では余り知られていないが、この時に重要な役割を果たしたのが国会議員であったあのジョン・スチュアート・ミルである。また法律制定に協力した主要な国会議員はほとんど保守党の議員であり、自由党の議員は誠に以て非協力的であった。この当時の自由党支持者の中心は企業経営者であったからであろう。今ではほとんど耳にすることがなくなってしまったが、かつてのイギリスでは時として「トーリー的民主主義」との言葉が行き交うことがあったのである。こうして1852年に「産業および節約組合法」が成立するのであり、そしてこの協同組合法は、三人の法廷弁護士(barrister)によって、すなわち、ニールが責任者となり、ラドローとヒューズが彼を支えて書き上げた法案に基づいているのである。
紙幅の都合でこれ以上、イギリスの労働者協同組合に関わる歴史を語ることができないが、私としては、先進諸国における現代労働者協同組合が幅広い運動を実践していることから、改めて先進諸国の現代労働者協同組合の歴史と現状を研究し、労協運動の社会的、経済的、文化的な発展可能性を論究していきたいと思っている。よりよき社会を追い求めて奮闘してきた菅野正純氏に後れを取らぬように。
(1) 大高研道「特集解題:労働者協同組合法と協同組合ネットワークの再構築―協同労働の地域的展開にむけて―」〔季刊〕『にじ』2021 SUMMER No.676(一般社団法人 日本協同組合連携機構)、2頁。
(2) 同上、3頁。
(3) 論点「労協法の成立:協同の可能性共有を」日本農業新聞、2020年12月21日(月)。
(4) 日本協同組合学会訳編『西暦2000年における協同組合』日本経済評論社、162頁。
(5) Tracts on Christian Socialism, No. V, p.1.
(6) Laws for the Government of the Rochdale Society of Equitable Pioneers, Rochdale, 1855, p.3.
|
◆2021年02月03日更新
◆労協法の成立 協同の可能性共有を (2020年12月21日、「日本農業新聞」WEB版)
12月4日、参院本会議において「労働者協同組合法」(労協法)が全会一致で成立した。私にとっても待ちに待った法案の成立である。
早速私は「法案概要」を取り出して「第1・目的」と「第2・労働者協同組合」に目を通し、この労協法の根本に「協同労働」という概念が示唆されていることを見て取った。
具体的には、①組合員による出資、②組合員の意見が反映された事業の遂行、③組合員自らが事業に従事することを基本原理とし、多様な就労の機会を創り出す、④地域における多様な希望・要求(需要)に応じた事業を行う、⑤持続可能で活力ある地域社会の実現に資する──である。なお、労協法は届け出れば設立できる「準則主義」であることも付け加えておこう。
役割一層重要に
この法案概要を見て、私は1999年11月に開かれた「労働者協同組合研究 国際フォーラム」での日本労働者協同組合連合会の元理事長、故・菅野正純氏の報告を思い起こした。
「協同の新しい可能性に向かって」と題した報告で、菅野氏は次のように提起した。①協同労働は雇用労働に代わる選択肢である②この選択肢を保障する社会制度を創り出すことの必要性③21世紀を目前にして、労協は組合員の利益のみならず、地域コミュニティーと社会全体の利益を追求する「21世紀型協同組合」としての「新しいワーカーズコープの法制度」を提案し、ボランティアや利用者と共に組合員が協同する協同組合、ハンディキャップを持つ人も組合員となり、労働する主人公になっていく協同組合を目指す④若者たちが人々の共感の中で自分らしい仕事を見いだして自分らしい人生を切り開いていくことへの援助が、これからの時代には重要な課題として労協に求められるだろう。
そして、菅野氏はこの援助のための基金にこう言及した。労協はその「公共的な使命」に対応する「新しい労協財政のあり方」を追求していく。それは、「組合員の営々たる労働のなかで作り出された剰余金、就労創出の積立金、福祉基金、それに教育基金」を組合員だけでなく、地域の他の人々も利用できる「新たな仕事起こしを実践する連帯支援資金」となるだろう。
「労働者本位」へ
菅野氏のこの「労協アイデンティティー」をヘーゲル哲学の「自立した個人は社会で生きる自覚を意識する」人々相互の「承認の必要性」を借りて言えば、人々にとって「労協に対する期待」「労協の果たすべき役割」「労協のなし得ること」とは何であるのかはおのずと明白になっていく、と私はひそかに思っている。その意味でも協同労働は「生活と人間性に不可分な労働」としての「労働者の裁量と自律性」を発揮するのにふさわしい「場」である、と私は確信している。
▽なかがわ・ゆういちろう 1946年静岡県生まれ。明治大学名誉教授。元日本協同組合学会会長。ロバアト・オウエン協会会長。著書『協同組合のコモン・センス』『協同組合は「未来の創造者」になれるか』(編著)などがある。
|
|